ホーム > 日本銀行について > 講演・記者会見・談話 > 講演・記者会見(2010年以前の過去資料) > 講演・挨拶等 2001年 > 日本金融学会における植田審議委員講演「流動性の罠と金融政策」
流動性の罠と金融政策
2001年9月29日・福島大学で開催された日本金融学会における植田和男審議委員による特別講演
- *本稿は、2001年9月29日・福島大学で開催された日本金融学会における植田和男審議委員による特別講演の内容を基に加筆修正したものである。
2001年10月 3日
日本銀行
[目次]
1.はじめに
私は1998年に学界を離れて日本銀行に移り、現実の金融政策運営に携わってきた。この間、学界からはさまざまな意見を頂戴し、大いに参考にさせていただいたが、こうした意見の中には現実の経済や金融政策に関する理解が必ずしも十分でないことによる誤解に基づくものもあったように思うし、学界の側にも「どうして日本銀行はもっと積極的に金融緩和策を進めないのか」といった不満があったかと思う。両者のギャップを埋めることは必ずしも容易ではないが、本日の講演では、日本銀行と学界との間のより良いコミュニケーションに資するよう努めたい。
この3年余りの金融政策を私なりに評価すれば、「できることが少ない中で、いろいろ考えてできるだけのことをやってきた」ということである。よく、短期金利がほぼゼロになって金利を下げる余地が少なくなったのであれば、次はベースマネーの量を増やせばよいとの意見を聞くが、これは必ずしも正しくないし、日本銀行はもう少しいろいろなことを考えながら金融政策を運営してきたというのが実感である。そこで、短期金利がほぼゼロの状態の下で何ができるのかについて理論的に整理した後、実際の政策運営を時間の流れを追って説明することとしたい。なお、残念であるが、今後の金融政策運営に関することについては、私の立場上あまり具体的にお話できない点をご了解いただきたい。
2.短期金利がゼロ近傍の下での金融政策
(1) 1990年代後半の金融政策に対する制約
1990年代後半の我が国においては、金融政策運営に対して大きく分けて2つの重大な制約が存在してきた。一つは、1995年後半より既に1%以下となっていた短期金利には、大幅な引下げ余地が残っていなかったという制約である。(図1参照。)もう一つは、金融機関が不良債権によって傷ついていたために、金融を緩和しても実体経済に対する景気浮揚効果が現れにくかったという制約である。
- 図1
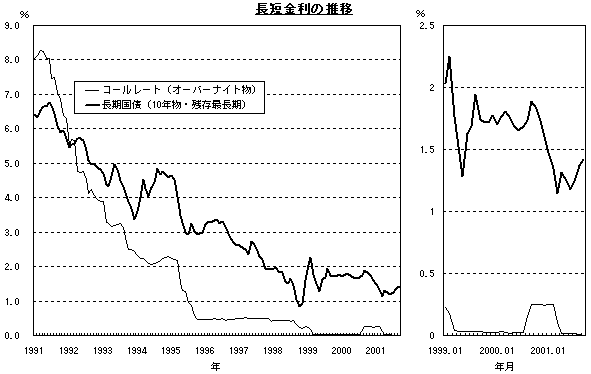
この間、経済学者を含む多くの人々が、日本銀行がベースマネーを十分増加させれば、物価は上昇するはずであるとの主張を展開してきた。しかし、この主張は今述べた金融政策に対する二つの制約を十分意識していないものと思われる。すなわち、ベースマネーと名目GDPとの関係を
Hv=PY
と書いたとしよう。ここに、H、P,Yはベースマネー、物価水準、実質GDP、さらにvはこの式で定義されるHとPYの比率である。Hを増やせば、物価や名目GDP(PY)が上昇するという主張は、vがあまり動かないとすれば正しい。しかし、図2にあるように、1990年代半ば以降はこの比率vが一貫して低下しており、ベースマネーを増やしても名目GDPが増加しにくい状況となっていた。しかも、ベースマネーに対する需要が「飽和」したため、ベースマネーを増加させること自体が難しいという局面もあった。通常、ベースマネーの増大は、金利の低下を引き起こし、財・サービスの需要につながっていく。その過程で、供給されたマネーは、金融機関等によって、財・サービスを購入する主体に貸し付けられる。金利の低下余地が限られ、金融セクターが傷ついていることによってこうしたメカニズムが働きにくくなってしまっているのである。1
- 図2
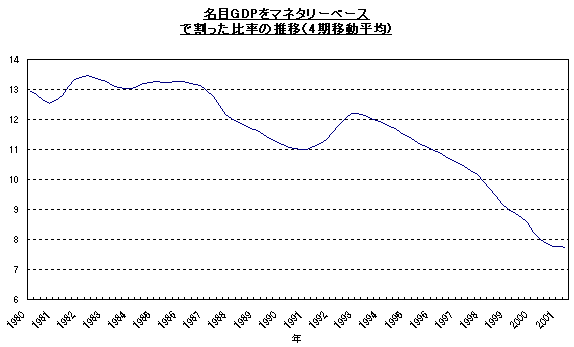
- 1この点は、単純なIS−LMモデルのような枠組みで考えるとわかりにくいかも知れないが、債券と銀行貸出が不完全に代替的であるという仮定を組み込んだモデルによって理解することができる。例えば、Bernanke and Blinder (1988)は、こうしたモデルにより、銀行の貸出供給関数が下方シフトすると、経済にデフレ効果をもたらすことを示している。
(2) 流動性の罠と金融政策のオプション
「流動性の罠」という概念についてはいろいろな解釈が存在し、若干の混乱もみられるが、ここでは単純に「名目金利に低下余地が無い状況」と定義することとしよう。こうした定義に沿えば、近年のわが国では、短期金融市場はほぼ流動性の罠に陥っていたということができよう。他方、長期金利に一段の低下余地が存在するか否かは難しい問題である。2
このように短期金利がゼロ近傍にある下でさらに金融を緩和したいと考えるなら、次の3つを候補としてあげることができよう。第1に、短期金利が低いとは言っても完全にゼロではないとすれば、ベースマネーを増やすことで、短期金利を限りなくゼロに近づけることができる。第2に、現在は金融緩和を追加的に行う余地が少ないことを踏まえ、将来の金融緩和を現在約束すること—いわゆる時間軸政策によって、経済主体の期待に働きかけることである。第3に、中央銀行が通常購入している短期国債などとは異なる資産を購入すること—いわゆる非伝統的なオペレーションを行い、こうした資産の価格に影響を及ぼすことである。
これら各々について敷衍することとしよう。まず、ベースマネーの供給増加については、これを続ければ短期金利を限りなくゼロに近づけることは可能であるが、その先は流動性の罠の状態となる。表現を変えれば、人々が短期金融資産でなく貨幣を保有しているのは、利子が得られなくても高い流動性等のメリットを感じているからである。均衡では追加的に貨幣を保有したときのメリットと、利子を生む資産でなく貨幣を保有するコスト、すなわち(名目)利子率が等しくなっているはずである。従って、短期金利がほぼゼロの下では、ベースマネーを保有することの限界的なメリットはほぼゼロとなっている。つまり、それ以上貨幣を供給しても何の意味も無いわけである。あるいは、人々がもう貨幣を要らないということになろう。実際に、日本銀行の資金供給オペにはしばしば「札割れ」という現象が生じた。さらに別な言い方をすると、短期国債の金利がほぼゼロの下では、ベースマネーと短期国債がほぼ完全な代替財となってしまう。同じ物同士を交換しても経済には何の影響も無い。
次に、既に短期金利がほぼゼロの下では、ベースマネーの供給増加—すなわち現在における量的緩和の効果が薄いことを踏まえ、将来にわたって金融緩和を続けるというコミットメントをするのが時間軸政策である。こうしたコミットメントを行うことで将来の短期金利に対する予想値を引き下げ、その結果、おおむねこれらの予想値の平均として決まる長期金利を引き下げたり、その他の資産価格に影響を及ぼすことで金融緩和効果を発揮させることとなる。3 加えてKrugmanは、こうしたコミットメントが経済主体のインフレ期待を高め、実質金利を引き下げることで、財・サービスに対する需要を直接高める効果を持つと主張している。
最後に、短期金利がほぼゼロ近傍の下ではベースマネーと短期国債はほぼ完全な代替財となるため、中央銀行がベースマネーとの代替性が低い資産—例えば、長期国債や外国為替に始まり、社債や株式、土地などを購入することで、その資産の価格変化を通じて金融緩和策を実行しうるという考え方がある。この場合、ベースマネーの増加は必ずしも必要ない。しかし、こうしたオプションの効果、潜在的なコストはきわめて不確実である。若干のコメントをすれば、上に見たように、時間軸政策には長期国債の価格を引き上げる、すなわち長期金利を引き下げるという狙いが既に含まれており、直接の買いオペとかなり近い効果を発揮する。ただし、長期国債がベースマネーや短期国債と完全に代替的でなければ、すなわちリスクプレミアムが存在すれば、その変化を通じて長期国債買いオペが長期金利を動かす可能性がある。4
また、外国為替市場への介入は日本銀行ではなく財務省の管轄である。なお、為替介入に関しては、非不胎化介入でなければ為替レートへの影響が減殺されると主張されることがあるが、短期金利がゼロ近傍にある下ではベースマネーと短期国債がほぼ完全な代替財となるため、不胎化を行うか否かはあまり意味がない議論であることを指摘しておきたい。むしろ、あまり指摘されていないことだが、短期金利ゼロ近傍では、財務省が短期国債を市場で発行して、外貨を買うという通常の不胎化介入を通じて、ほぼ金融緩和政策を実行できるのである。なぜなら、発行された短期国債はほぼベースマネーに等しいからである。
- 2なお、ケインズが定義した流動性の罠とは、長期金利が極限まで低下し、そこから先はむしろ金利上昇、キャピタルロスを恐れて、人々が長期債投資よりも貨幣を保有することを選好する。そのためそれ以上長期金利が低下しない状況であるが、これは果たして安定的な均衡となりうるかどうかという問題は理論的に興味深い。わが国の例で言えば、1998年には長期金利がいったん0.7%台まで低下した後、その後1~2ヵ月の間に2%台まで大きく反転上昇したことがあったが、これなどはケインズの意味での流動性の罠が出現したと考えることはできるだろうか。興味深い研究テーマと思う。
- 3より厳密には次のような点も議論されてきた。すなわち、市場参加者が合理的なら金利をゼロに据え置くのが適当と思われる間は、中央銀行は当然そうすると考えるだろう。従って、将来の金融緩和策の約束が意味を持つのは、通常は金利を引き上げるのが適当という状況になっても、しばらくそれをしないという約束をすることである。しかし、仮にここまで踏み込まなかったとしても、将来の金融緩和に関する強いコミットメントは、通常避け難い将来の金融政策に関する不確実性を低下させることによって、緩和効果を発揮しよう。詳しくは、植田(2000)参照。
- 4一般に、長期金利は将来の短期金利予想値の平均にリスクプレミアムが加わったものと理解できる。長期国債を直接買わなくても時間軸効果が効いていれば、将来の短期金利予想値を動かすことによって、長期金利に強い影響が及ぶ。さらに、かりに日本銀行の買いオペ増額がリスクプレミアムを下げる方向に働けば、追加緩和効果が生まれる可能性があるということである。
3.1990年代後半の金融政策
(1) 1997年~1998年の流動性危機と金融政策
次に、これまでの理論的整理をもとに、1990年代後半の金融政策運営を時間を追ってみていくこととしたい。最初に1997年から1999年にかけての時期をとりあげよう。1997年に三洋証券などの金融機関が破綻した後、1998年にも長銀、日債銀が破綻するなど金融システムが不安定化し、ロシア国債のデフォルトを契機とした国際金融市場の混乱なども加わったため、邦銀に対する信認が低下し、ドル資金調達金利に対するジャパン・プレミアムが拡大した。国内においても、金融機関による流動性需要が増大したため、短期金融市場で、例えばコールマネーのオーバーナイト物とユーロ円の3ヵ月物とのスプレッド—すなわちタームプレミアムが拡大したほか、こうしたプレミアムの金融機関相互間での格差も拡大した。いわば、流動性ないしクレジット・クランチが発生し、銀行貸出と民間企業の設備投資はともに急速に減少した。
これに対する日本銀行の対応は、上にみた3つの政策オプションを全て動員したということができよう。すなわち、日本銀行はまず1998年9月から1999年3月にかけて、ベースマネーの供給増加を通じて短期金利をゼロに向かって引き下げた後、1999年4月にはゼロ金利を「デフレ懸念が払拭されるまで」維持するとのアナウンスメント—時間軸政策そのものを採用した。さらに、CPを対象とする買入れオペを拡大したり、社債や資産担保証券をオペの適格担保に加えたり、金融機関の貸出増加額に応じて日本銀行がバックファイナンスを行うといった、ある意味では非伝統的オペともみられる手段を実施している。
さて、1999年4月以降も、日本銀行に対して「量的緩和」策を求める声は多かった。しかしながら、こうした主張は当時の金融政策に関する十分な考察に基づいていたとは言い難い。第一に、短期金利がゼロ近辺に低下してしまえば、それ以上のベースマネーの拡大という意味での量的緩和にあまり意義を認めがたいことは上に述べた通りである。第二に、しばしば「量的緩和」の権化のようにいわれるKrugmanも、流動性の罠の下では単純なベースマネーの拡大という量的緩和に意味が無いということを認めた上で、別の政策を提案しているのである。すなわち、現在だけでなく将来もインフレ率が高くなるまで金融緩和を続けるという約束が、期待インフレ率を現在高めるという意味で金融緩和効果を持つと主張しているのである。さらに、こうした約束はインフレ率が上昇しても金利を上げないというコミットメントでも代替できると指摘している。5 振り返ってみれば、1999年4月以降の日本銀行のゼロ金利政策、すなわち「デフレ懸念払拭までゼロ金利を継続する」は、こうした主張とほぼ同様の枠組みであったし、弱い意味でのインフレーション・ターゲティングであったとも言える。つまり、Krugman流の「量的緩和」をまさに実行していたのである。こうした点が、なかなか専門のエコノミストにも理解されなかったのは残念であるとともに不思議な現象であった。ただ、日本銀行の「約束」はややあいまいなものであったし、Krugmanはインフレ率が「年率4~5%になるまで」と主張していたのに対し、日本銀行はそこまでのコミットメントはしていなかったという重要な相違は残っていた。
- 5Krugman (1998)参照。
(2) 景気回復と2000年の利上げ
その後の日本経済は、日本銀行によるゼロ金利政策の継続とともに、金融機関への公的資金の注入、中小企業信用保証制度の拡充(特別保証の導入)などによって流動性危機が緩和されたことによって、設備投資や個人消費が回復したほか、いわゆるITブームあるいはITバブルの中で電気機械産業を中心として輸出→生産→企業収益→設備投資という好循環が生じたことなどから景気回復局面に入った。このため、2000年夏ごろには潜在成長率以上の成長も可能との見方も現れ、日本銀行の政策委員会においても、景気が拡大してGDPギャップが縮小していることを理由に利上げの必要性を指摘する意見が大勢となった。
しかし、ゼロ金利政策を解除するためには、政策金利の適正水準自体が具体的にどこにあるのかを知る必要があった。そして、仮にGDPギャップが縮小しているのが事実だとしても、そのことだけからは、適正金利が上昇しているという結論は導かれても、その水準がプラスなのかマイナスなのかを知ることはできない。ゼロ金利政策の下では、適正金利が本当はマイナスであるのに実際の金利はゼロという下限に張り付いていたかもしれないのである。当時、私自身はいわゆるTaylor Ruleによって適正金利の具体的な水準を試算してみたが、その結果は、適正金利は上昇しつつあったが水準はなおマイナスというものであった。単純化して言えば、このような認識こそが2000年8月のゼロ金利解除に私が反対した理由である。ただ、このような試算については、その前提を大きく変えれば当時の適正金利の水準をプラスと導くことも可能であることを付け加えておきたい。このように適正金利の水準を厳密に算出することは非常に難しく、この点はある意味では現在の経済学の限界を示しているようにも思う。
(3) 2000年第4四半期からの景気後退と2001年3月の金融緩和
2000年末にかけて、ITブームおよび米国景気の失速が明らかとなり、その後、わが国においても製造業中心に急速な落ち込みが生じた。この間、非製造業部門は総体としては停滞を続けていたほか、財政政策も引締め気味に推移してきたこともあって、わが国景気の先行きに対する見方は急速に悪化した。このため、日本銀行は2001年に入り、2月に若干の金利引下げ後、3月には金融緩和策を大幅に拡充した。具体的には、金融政策の操作目標をコールレートから日銀当座預金残高に変更し、その目標を当初は5兆円に増やす(それ以前は平均的には約4兆円で推移)とともに、目標達成のために必要であれば長期国債の購入も増加させるというものであり、さらに、こうした政策を消費者物価指数の前年比上昇率がゼロを安定的に上回るまで続けるというコミットメントが加えられていた。
この金融政策の枠組みも、上の2.でみたような金融政策の3つのオプションを全て含んでおり、かつてのゼロ金利政策と極めて近いものである。ベースマネー供給の増加によって短期金利はほぼゼロの水準まで低下したほか、政策についてのコミットメントは、「ゼロ金利をプラスのインフレ率まで続ける」ことと、厳密に同じではないが、大体等しい。さらに、こうしたコミットメントは、それ自体で将来の短期金利に対する予想値を引き下げることを通じて長期金利を引き下げる効果を持っており、長期国債の購入を実際に増加させなくても、それと同様の効果を発揮することが期待できる。
他方で、この枠組みとゼロ金利政策には若干ながら相違点も存在する。すなわち、この枠組みにおいては完全なゼロ金利は約束されていないので、何らかの理由で流動性需要が増加した場合には短期金利が上昇する。その意味ではゼロ金利政策のほうが緩和効果が強い面がある。ただ、すぐ下で見るように、この枠組みの下でベースマネーを大幅に増加させたことによって、平均的には、前回のゼロ金利政策の時期以上に短期金利はゼロへ接近したという予想外の効果もあった。両方合わせれば、日銀当預を目標とした現行スタンスは、当預目標を増大させることによって、前回よりも低い「ゼロ金利」へと徐々に接近する、すなわちステップを刻むことを可能にする枠組みであるといえよう。6 また、現行枠組みにおけるコミットメントは前回のゼロ金利政策における「デフレ懸念が払拭されるまで」という内容よりも明確である。さらに、長期国債の購入増加は、リスクプレミアムの減少というルートを通じて長期金利を引下げるという可能性も含んだ枠組みである。
3月の金融緩和によって、金融市場では6月にかけて、短期金利のほぼゼロ金利化や中長期金利の低下(ただし、4月頃には財政要因等から10年国債の金利は上昇)、株価の上昇、円相場の軟化といった効果が観測された。これらの効果は前回のゼロ金利政策の際とほぼ同様である。ただ、上に見たKrugmanの主張が正しければ、こうした金融緩和の実施によって期待インフレ率の上昇が観測されるはずであるが、市場関係者に対するサーベイ調査を見ると、1~2年先の期待インフレ率は単調に低下してきている(図3参照)。期待インフレ率の動きについては、以下でもう少し詳しく論じたい。
- 図3
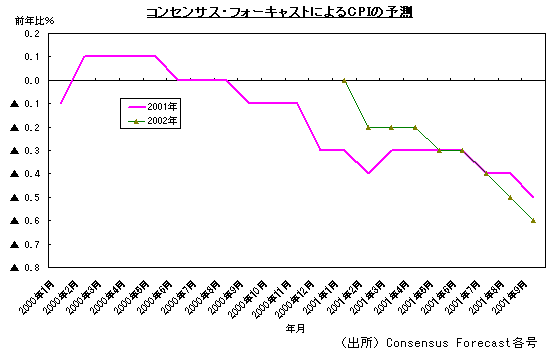
- 6この他に大幅な日銀当座預金の供給は、金融機関によるポートフォリオ・リバランス効果を引き起こすのではという期待も一部にあったが、こうした効果は現在までのところはっきりとは確認されていない。
(4) 8月以降の追加緩和とその評価
先行きの景気・物価動向に関する見方の一段の悪化に対応して、日本銀行は8月にも、日銀当座預金残高目標の6兆円への引上げと長期国債購入額を50%増大させるという追加的な金融緩和策を採用した。その結果、コール市場での手数料率の引き下げや金利の最小単位の引下げ(0.01%→0.001%)もあって、図4にあるように、短期金利は一段とゼロへと接近した。現状では、100億円をコール市場でオーバーナイト運用してもわずか数百円の利子しか得られず、短期金利の低下はほぼ限界に達しつつあると見られる。しかし、長期金利はかえって上昇したほか、株安と円高が進行し、金融緩和の効果は捗々しくなかった。
- 図4
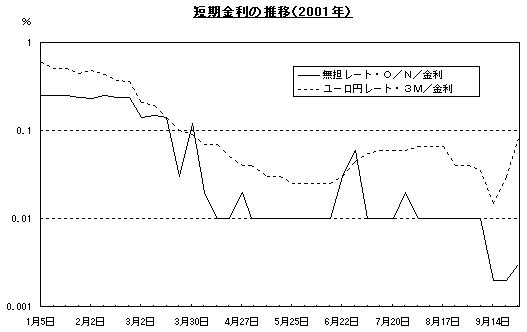
8月の追加緩和策の効果を一言で評価すれば、短期金利がほぼゼロの下でのベースマネーの増加や長期国債の購入の効果は小さかったということになろう。このような結論は、上の2.での理論的整理と整合的である。ベースマネーの増大は、短期金利を低下させることによって緩和効果をもたらす。8月の措置以降のオーバーナイト金利低下幅は、1ベーシスポイント以下に過ぎなかった。長期債購入については、それに近い効果をもたらす強力な時間軸効果が既に導入されていたこともあり、長期金利は低下しなかった。むしろ、金融緩和に前後してインフレーション・ターゲティングの導入に関する議論が盛んに行われたこともあって、かなり先の期間におけるインフレのリスクが意識された結果、長期金利の上昇が生じたものと考えられる。図5は長期金利から計算される1年物インプライドフォワード・レートを示している。ここには興味深い動きが現れている。金融緩和措置の前後(13日→15日)で、各レートは上昇している。さらにインフレーション・ターゲティングの議論が高まった21日にかけては一段の金利上昇が観察される。しかし、小泉総理をはじめとしてインフレーション・ターゲティングに慎重な発言が相次ぐと、24日にかけて(9年先スタートのレートを除いて)レートは低下した。こうした動きが、期待インフレ率の変動なのか、インフレリスクプレミアムの動きなのかを厳密に峻別することは難しいが、7 いずれにせよ、7年先以降のようなかなり先の期間の金利については、金融緩和の実施やインフレーション・ターゲティングに関する議論の高まりに敏感に上昇方向で反応したのである。先に見たように、この間、より一般的な期待インフレ率は低下を続けていた。8 これは予想のホライズンによって期待インフレ率が異なるということかもしれないし、債券市場の参加者とより一般の人々の期待が異なるということかもしれない。いずれにせよ、こうした場合、長期国債の購入増加やインフレーション・ターゲティングの導入は、設備投資や個人消費に影響を与えると思われる短期ないし一般の企業・家計の期待インフレ率は上昇しない一方、遠い先のインフレ懸念から長期金利は上昇してしまうという意味で、むしろデフレ的という可能性もある。9 もちろん、こうした結果が常に発生するとは限らない。しかし、長期債購入増加がもたらすリスクとして認識しておくことは重要と思われる。
- 図5
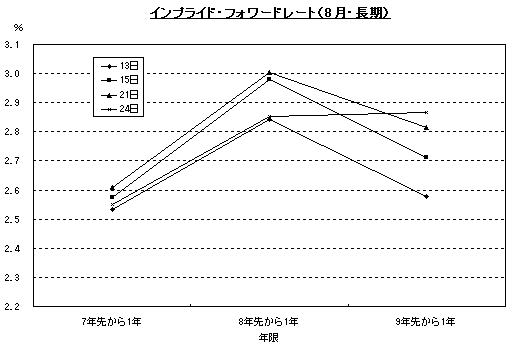
9月に入り、米国での同時多発テロ事件を契機として、金融市場では不安心理が高まった。こうした不安心理による流動性需要が増加したため、直ちに9月12日から日本銀行は日銀当座預金残高をそれまでの約6兆円から約8兆円へと増加させて対応した。しかし、期末要因、国債決済リスク懸念等により短期金融市場ではターム物やレポ・レートの上昇が続いたこともあり、18日の金融政策決定会合において金融調節方針を正式に変更し、日銀当座預金残高の目標を当面6兆円以上とすることとした。10 目標を特定の金額にしなかったのは、不安心理がいつ落着くか見通し難い状況であったことに加え、いったん不安心理が落着けば流動性需要が減少するため、例えば8兆円といった特定の金額を継続して供給し得るか否かが明らかでなかったためである。現実には、短期金融市場の動揺を抑えるための資金供給は9月末にかけて一段と増大し、日銀当預は28日には12兆円を越えることになった。
9月の措置に関連して付け加えれば、現在のように日銀当座預金というマネーの量を目標とした政策運営の下では、流動性需要が急に高まると、場合によっては、当座預金目標を増大するという調節方針の変更なしでは金利上昇を招いてしまうという問題がある。これは、既に指摘したとおり、現行方針が完全なゼロ金利政策ではないためである。他方、ゼロ金利政策であれば、こうした流動性供給は自動的に実施される。また、9月後半の流動性供給のすべてがそうだと言いきる訳ではないが、こうした金融不安等に対応した流動性供給増大は通常の意味での金融緩和策ではないし、逆に不安心理後退に伴って流動性供給が減ったとしても、それは金融引締めではない点に注意が必要である。
- 7さらに言えば、その他の要因によってこうしたインプライド・フォワード・レートの動きが生じた可能性ももちろんある訳である。
- 8同様の例は、1997年5月のイギリスの経験にも見られる。当時、イングランド銀行の金融政策運営の独立性をより高めるような意思決定がアナウンスされると、ほぼ瞬時的に物価インデックス債市場から計算されるインプライド・フォワードのインフレ率は特に4、5年より先のホライズンで大きく低下した。しかし、その前後の一般国民への期待インフレ率調査では、現実のインフレ率の足許の上昇に沿った形で期待インフレ率の上昇が確認されている。(図6参照)
- 図6
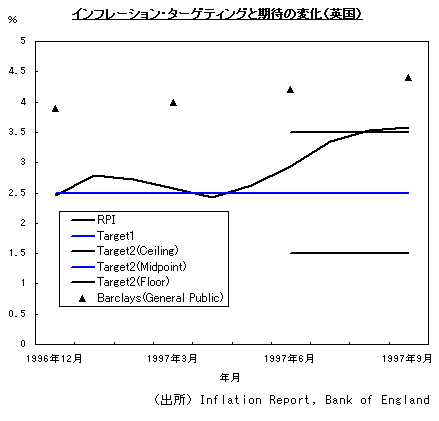
- 図6(続き)
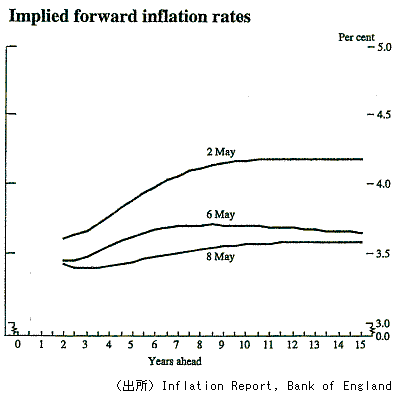
- 9少なくとも、長期金利上昇は長期債を多く保有する金融機関にキャピタル・ロスを発生させる。
- 10この他、公定歩合を0.10%へ引き下げることを決定した。
(5) インフレーション・ターゲティング論を巡って
上の議論から明らかなように、現行の金融政策枠組みの何割かはインフレーション・ターゲティング的であり、残りの何割かはインフレーション・ターゲティング的でないといえる。すなわち、現行の枠組みを止める時期を消費者物価指数上昇率に関連付けている点ではインフレーション・ターゲティング的である。なお、ゼロインフレに到達するまで現行枠組みを維持するとしているが、インプリシットな、より中長期の目標インフレ率はゼロではなく若干のプラスと解釈することも可能であることを指摘しておきたい。なぜなら、景気が回復し始め、現実のインフレ率と期待インフレ率がほぼゼロに戻ったとしよう。それでも日本銀行は名目短期金利をほぼゼロのままに据え置くとすれば、実質金利もほぼゼロであり現在よりも低く、景気刺激的である。この結果、暫くは消費者物価指数上昇率が上昇すると考えられるからである。他方で、現在の枠組みにおいては、消費者物価指数上昇率がゼロを超える時期を明示している訳ではないという点ではインフレーション・ターゲティング的でない。
インフレーション・ターゲティングについて、私自身は、景気やインフレ率が正常な水準に戻った後であれば、一つの政策オプションになりうると考えている。これに対して、現在のようなデフレ下でも、日本銀行がゼロインフレの達成目標時期を明示すれば、経済主体のインフレ期待が上昇するため金融緩和効果を発揮するはずであるとの主張がみられる。しかし、私は、景気を刺激するための金融政策手段が限られている現状では、こうした達成目標時期を明示しても、市場の冷ややかな反応を招くに止まり、政策手段とならないどころか金融政策に対する信認を失わせる結果となるのではないかと懸念している。加えて、先にみたように、企業・家計のインフレ期待は上昇しない一方、債券市場では長期のインフレリスクを気にするといった反応となれば、かえって事態を悪化させるリスクもありえよう。11
- 11もちろん、日銀法を改正して、日銀が何を買っても良い(例えば、耐久消費財)ようにするというのであれば、デフレ収束の時期を明示化することも可能だろうし、むしろインフレを一定限度以下に抑えるというためのインフレーション・ターゲティングが必要となろう。
4.おわりに—流動性の罠の下でのポリシーミックス
最後に、流動性の罠の下での金融政策運営について、ポリシーミックスの観点から議論することとしたい。
一般論として、物価は金融政策のみでは決まらない。物価は財・サービスの需給を反映して決まるのであり、供給側を取り敢えず措くとしても、需要側は金融政策だけでなく、家計・企業の行動に影響する様々な変数の動きや財政政策にも影響を受けることとなる。12 さらに、冒頭に指摘したように、金融政策の物価制御能力は大きく低下しているのが現状である。
現在の金融政策の枠組みは、大まかに言えば短期金利をほぼゼロに維持する政策をゼロインフレまで続けるということであるが、ゼロインフレに到達する時期は、むしろ、財政政策を含めた政府の他の経済政策によって決まるということではないかと思う。デフレの悪影響が非常に心配で、ゼロインフレへの到達をできるだけ早めたいというのであれば、政府が思い切った拡張的財政政策—例えば非リカーディアン的財政政策—を実施することが考えられる。確かに、国債の発行残高がこれ以上増加することには不安もあろうが、現在は、大規模な財政政策を実施することが全く不可能な状況でもないようにも思う。ただ、この場合デフレは収まったとしても、中長期的な経済の姿が本格的に改善するかどうかは別の問題である。このようなポリシーミックスが望ましくなければ、不良資産問題を含む構造改革を真剣に進めるという方法もある。構造改革路線の方がゼロインフレに到達するまでには比較的長い期間を要するかもしれない一方で、最終的に出現する経済はより効率的で望ましい姿になるかもしれない。どちらが良いか、あるいは他のより良いポリシーミックスがあるか、決定権は政府にある。
- 12財政政策と物価の関係については、例えば、発展途上国におけるハイパーインフレーションの収束には財政規律の回復が重要であるとされてきた。また、最近の「物価水準の財政理論 (Fiscal Theory of Price Level) 」によれば、デフレスパイラルを回避するためには、財政当局が国債残高があまり減らないように、拡張的財政政策を行うとともに将来の増税もしないと約束するいった「非リカーディアン的財政政策」を行うことが有効であるとされる。なぜなら—全てがこのように上手くいくかどうかはわからないし、こうした政策を推奨している訳でもないが—将来の増税を伴わない減税策は、消費を刺激して物価を上昇させるし、それが既存の政府債務の実質価値を低下させて財政のほうもつじつまが合ってしまうのである。(Woodford (2000)参照。)
参考文献
- 植田和男(2000)「ゼロ金利近傍における金融政策の波及メカニズム」日本銀行調査月報、11月号
- Bernanke, Ben and Alan Blinder (1988):"Credit, Money and Aggregate Demand",
American Economic Review Papers and Proceedings, vol. 78, No.2, pp.435-439 - Krugman, Paul (1998):"It's Baaack: Japan's Slump and the Return of the Liquidity Trap",Brookings Papers on Economic Activity, No.2., pp.137-205
- Woodford, Micheal (2000):"Fiscal Requirements for Price Stability",
NBER Working Paper Series, No.8072