経済・物価情勢の展望(2018年7月)
基本的見解 1
2018年7月31日
日本銀行
概要
- 日本経済の先行きを展望すると、2018年度は海外経済が着実な成長を続けるもとで、きわめて緩和的な金融環境や政府支出による下支えなどを背景に、潜在成長率を上回る成長を続けるとみられる。2019年度から2020年度にかけては、設備投資の循環的な減速や消費税率引き上げの影響を背景に、成長ペースは鈍化するものの、外需にも支えられて、景気の拡大基調が続くと見込まれる2。
- 消費者物価(除く生鮮食品)の前年比は、プラスで推移しているが、景気の拡大や労働需給の引き締まりに比べると、弱めの動きが続いている。これに伴って、中長期的な予想物価上昇率の高まりも後ずれしている。
- 経済・雇用情勢の改善に比べて、物価上昇率の高まりに時間を要している背景には、長期にわたる低成長やデフレの経験などから、賃金・物価が上がりにくいことを前提とした考え方や慣行が根強く残っていることがある。こうしたもとで、企業の慎重な賃金・価格設定スタンスや家計の値上げに対する慎重な見方が、明確に転換するには至っておらず、分野によっては競争激化による価格押し下げ圧力が強い。企業の生産性向上余地の大きさや近年の技術進歩などが、それらに影響している面もある。
- もっとも、マクロ的な需給ギャップがプラスの状態が続くもとで、企業の賃金・価格設定スタンスが次第に積極化し、家計の値上げ許容度が高まっていけば、実際に価格引き上げの動きが拡がり、中長期的な予想物価上昇率も徐々に高まるとみられる。この結果、消費者物価の前年比は、これまでの想定よりは時間がかかるものの、2%に向けて徐々に上昇率を高めていくと考えられる。
- 従来の見通しと比べると、成長率は概ね不変、物価については下振れている。
- リスクバランスをみると、経済については、2018年度はリスクは概ね上下にバランスしているが、2019年度以降は下振れリスクの方が大きい。物価については、下振れリスクの方が大きい。物価面では、2%の「物価安定の目標」に向けたモメンタムは維持されているが、なお力強さに欠けており、引き続き注意深く点検していく必要がある。
1.わが国の経済・物価の現状
わが国の景気は、所得から支出への前向きの循環メカニズムが働くもとで、緩やかに拡大している。海外経済は、総じてみれば着実な成長が続いている。そうしたもとで、輸出は増加基調にある。国内需要の面では、設備投資は、企業収益や業況感が改善基調を維持するなかで、増加傾向を続けている。個人消費は、雇用・所得環境の着実な改善を背景に、振れを伴いながらも、緩やかに増加している。この間、住宅投資は横ばい圏内で推移している。公共投資も高めの水準を維持しつつ、横ばい圏内で推移している。以上の内外需要の増加を反映して、鉱工業生産は増加基調にあり、労働需給は着実な引き締まりを続けている。わが国の金融環境は、きわめて緩和した状態にある。物価面では、消費者物価(除く生鮮食品、以下同じ)の前年比は、0%台後半となっている。予想物価上昇率は、横ばい圏内で推移している。
2.わが国の経済・物価の中心的な見通し
(1)経済の中心的な見通し
先行きのわが国経済は、緩やかな拡大を続けるとみられる。2018年度についてみると、国内需要は、きわめて緩和的な金融環境や政府支出による下支えなどを背景に、企業・家計の両部門において所得から支出への前向きの循環メカニズムが持続するもとで、増加基調をたどると考えられる。すなわち、設備投資は、緩和的な金融環境のもとで、景気拡大に沿った能力増強投資、オリンピック関連投資、人手不足に対応した省力化投資を中心に、増加を続けると予想される。個人消費も、雇用・所得環境の改善が続くもとで、緩やかな増加傾向をたどるとみられる。公共投資は、2017年度補正予算やオリンピック関連需要もあって高めの水準を維持すると予想している。輸出についても、海外経済の着実な成長を背景に、基調として緩やかな増加を続けるとみられる。こうしたもとで、2018年度は、潜在成長率3を上回る成長を続けると見込まれる。
2019年度と2020年度については、内需の減速を背景に成長ペースは鈍化するものの、外需にも支えられて、景気の拡大基調が続くと見込まれる。すなわち、個人消費は、2019年10月に予定されている消費税率の引き上げの影響4から一時的に減少に転じるなど、2019年度、2020年度ともに緩やかな増加ペースにとどまると予想される。もっとも、海外経済の着実な成長を背景に、輸出は増加基調を維持すると見込まれる。この間、設備投資は、景気拡大局面の長期化による資本ストックの積み上がりやオリンピック関連需要の一巡などから、2020年度にかけて増勢が徐々に鈍化していくとみられるが、輸出の増加を起点とした投資需要の高まりもあって、増勢鈍化のペースは緩やかなものになると予想される。なお、今回の成長率の見通しを従来の見通しと比べると、概ね不変である。
こうした見通しの背景となる金融環境についてみると、日本銀行が「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を推進するもとで、短期・長期の実質金利は見通し期間を通じてマイナス圏で推移すると想定している5。また、金融機関の積極的な貸出スタンスや社債・CPの良好な発行環境が維持され、企業や家計の活動を金融面から支えると考えられる。このようにきわめて緩和的な金融環境が維持されると予想される。
この間、潜在成長率については、政府による規制・制度改革などの成長戦略の推進や、そのもとでの女性や高齢者による労働参加の高まり、企業による生産性向上に向けた取り組みなどが続く中で、見通し期間を通じて緩やかな上昇傾向をたどるとみられる。
(2)物価の中心的な見通し
わが国の物価は、マクロ的な需給ギャップが需要超過となるもと、前年比プラスの状況が続いている。もっとも、景気の拡大や労働需給の引き締まりに比べると、企業の慎重な賃金・価格設定スタンスなどを背景に、なお弱めの動きを続けている。こうした中、中長期的な予想物価上昇率は横ばい圏内となっており、その高まりが後ずれしている。
先行きの物価を展望すると、マクロ的な需給ギャップがプラスの状態が続くもとで、企業の賃金・価格設定スタンスは次第に積極化し、中長期的な予想物価上昇率も徐々に高まってくるとみられる。この結果、消費者物価の前年比は、これまでの想定よりは時間がかかるものの、2%に向けて徐々に上昇率を高めていくと考えられる。なお、今回の物価の見通しを従来の見通しと比べると、下振れている6。
- (i)物価上昇に時間を要している背景7
2013年4月の「量的・質的金融緩和」導入以降、わが国の経済・雇用情勢は大きく好転し、マクロ的な需給ギャップも、はっきりと改善した。こうしたもとで、エネルギー価格の影響を除いた物価上昇率はプラス圏での推移が定着しており、わが国は、「物価が持続的に下落する」という意味でのデフレではなくなった。
もっとも、経済・雇用情勢の改善に比べて、物価や予想物価上昇率の改善ペースは、緩慢なものにとどまっている。この背景には、基本的に、長期にわたる低成長やデフレの経験があると考えられる8。1990年代後半の金融危機やその後の世界金融危機を含む厳しい調整局面を経て、企業の慎重な賃金・価格設定スタンスや値上げに対する家計の慎重な見方、言い換えれば、賃金・物価が上がりにくいことを前提とした考え方や慣行が経済に組み込まれ、その転換に時間を要している。加えて、非製造業を中心に生産性を引き上げる余地が大きいことや、デジタル化といった近年の技術進歩などは、経済が拡大する中にあっても、企業が値上げに慎重なスタンスを維持することを可能にし、分野によっては競争環境を厳しくしている面もあるとみられる。
このように、低成長やデフレの経験が生産性向上余地の大きさなどと相俟って、わが国では、物価のマクロ的な需給ギャップへの感応度が高まりにくく、適合的な期待形成の力が強い予想物価上昇率も上がりにくい状況が、想定以上の期間にわたって、続いていると考えられる。こうした物価や予想物価上昇率が上がりにくくなっている要因を、家計や企業の行動面から整理すると、以下のとおりとなる。
第1に、企業の賃金設定スタンスがなお慎重であり、本格的な賃金上昇の実現に時間がかかっている。パート時給ははっきりとした上昇基調を続けている一方、正規雇用者の所定内給与は伸び悩んでいる。これには、低成長下での雇用調整の経験もあり、正規雇用者が賃金引き上げより雇用の安定を優先する傾向が根強いことも影響している。企業側も、中長期的な成長期待が十分に高まらないこともあって、賃金の引き上げにはなお慎重である。さらに、最近になって女性や高齢者の労働参加が一段と高まっていることは、家計全体の所得増加に繋がる一方、賃金そのものに対しては、弾力的な労働供給を通じて、上昇ペースを緩める方向に作用している。これらは、マクロ的な需給ギャップが改善しても賃金が上昇しにくい要因となっているほか、予想物価上昇率が高まりにくい一因ともなっている。
第2に、家計の値上げに対する許容度が明確には高まっていない。本格的な賃金上昇の実現に時間がかかっていることに加え、先行きの経済成長や社会保障制度に関する慎重な見方が根強いことも、値上げ許容度の高まりの遅れにつながっている面があると考えられる。
第3に、仕入価格が上昇し、賃金コストが緩やかながら着実に増加しているもとでも、企業の価格設定スタンスはなお慎重である。家計の値上げに対する許容度が明確に高まらない中、デフレ下での価格競争の経験もあって、マクロ的な需給ギャップが改善するもとでも、値上げによる顧客離れを警戒する企業はなお少なくない。こうしたもとで、企業は、省力化投資の拡大やビジネス・プロセスの見直しなど、コスト上昇圧力の吸収に向けた取り組みを強化している。非製造業を中心に生産性を引き上げる余地が大きいことや、近年のデジタル技術の進歩が、企業のこうした取り組みを可能にしている面もあるとみられる。
第4に、競争環境が厳しさを増していることに伴う価格押し下げ圧力が、いくつかの分野で働いている。例えば、携帯電話関連で断続的な値下げがみられているほか、スーパーなどでは、インターネット通販の拡大等を背景に、慎重な価格設定スタンスが続いている。これらは、一般的には、特定部門に固有のショックであり、その影響は長期的には減衰していく性質のものと考えられる。ただし、最近では、デジタル技術の進歩もあって、こうした動きが幅広い分野で継続的に発生しており、消費者の根強い低価格志向や適合的な期待形成メカニズムと相俟って、長期にわたり一般物価の押し下げ圧力として働いているとみられる。
このほか、以上とはやや性質を異にするが、消費者物価指数において相応のウエイトを持つ公共料金や家賃などが鈍い動きを続けていることも、物価の上がりにくさに影響していると考えられる。
- (ii)物価上昇率が高まるメカニズム
このように、複数の要因が複合的に作用してきたことから、物価上昇率の高まりには時間を要しているが、最近では、業種や規模を問わず幅広い企業で、販売価格の引き上げに向けた動きがみられ始めている。また、積極的な設備投資計画からも窺われるように、経済・雇用情勢が持続的に改善するもとで、企業の将来に対する見方も変化しつつあるとみられる。
先行きを展望すると、景気の拡大基調が続く中で、物価の上昇を遅らせてきた要因の多くは次第に解消していくと考えられる。技術進歩の影響などは先行き強まる可能性もあるが、労働需給が引き締まった状態が続くもとで、賃金上昇率の高まりはより明確化していくとみられる。こうしたもとで、外食などのサービス業で既にみられ始めているように、販売価格への上昇圧力は強まっていくとみられるほか、人手不足を背景とする物流コストの増加は、インターネット通販企業のコスト面での競争力を弱めることを通じて、小売業との競争環境を緩和させる方向に作用することも考えられる。さらに、労働生産性の上昇や非正規雇用者の賃金水準の高まりが、正規雇用者の賃金に波及していけば、家計の値上げ許容度も全体として徐々に高まり、企業による値上げはより受け入れられやすくなるとみられる。また、高齢者の労働参加の高まりを支えてきたいわゆる団塊世代が70歳代に達しつつあることなどを踏まえると、労働参加の高まりが賃金を抑制する効果も緩やかになっていくことが予想される。
このように、消費者物価の上昇を抑制してきた要因が次第に解消し、その前年比が2%に向けて徐々に上昇率を高めていく姿を、一般物価の動向を規定するマクロ的な需給ギャップや中長期的な予想物価上昇率などに基づいて整理すると、以下のとおりとなる。
第1に、労働や設備の稼働状況を表すマクロ的な需給ギャップは、労働需給の着実な引き締まりや資本稼働率の上昇を背景に、プラス幅を拡大している。先行きについても、わが国経済が緩やかな拡大を続けるもとで、マクロ的な需給ギャップは2018年度にプラス幅をさらに拡大し、2019年度から2020年度についても比較的大幅なプラスで推移するとみられる。このように、マクロ的な需給ギャップがプラスの状態が続くもとで、企業の賃金・価格設定スタンスが積極化し、家計の値上げ許容度が高まっていけば、実際に価格引き上げの動きが拡がっていくと考えられる。
第2に、中長期的な予想物価上昇率は、足もとは横ばい圏内で推移しているが、先行きについては、上昇傾向をたどり、2%に向けて次第に収斂していくとみられる。この理由としては、まず、「適合的な期待形成」9の面では、先ほど述べたように、実際に価格引き上げの動きが拡がっていけば、これが、現実の物価上昇率の伸びを通じて、予想物価上昇率を押し上げていくと期待される。また、「フォワードルッキングな期待形成」の面では、日本銀行が「物価安定の目標」の実現に強くコミットし金融緩和を推進していくことが、予想物価上昇率を2%に向けて押し上げていく力になると考えられる。
第3に、輸入物価についてみると、最近の原油価格の上昇は、2018年度の消費者物価の押し上げ要因として作用するが、その影響は緩やかに減衰していくと予想される。
この間、先ほど指摘したように、最近になって顕著となっている女性・高齢者の労働参加の高まりや、企業の生産性向上によるコスト上昇圧力の吸収に向けた取り組みの強化は、短期的には賃金や物価の上昇圧力を弱める方向に作用するとみられるが、より長い目でみれば、上昇圧力を高める方向に作用していくと予想される。すなわち、こうした動きは、労働人口の減少といった構造的な問題を軽減し、日本経済全体の生産性を高め、成長力強化に繋がる可能性がある。人口減少などを理由に期待成長率を低めにみる企業経営者も少なくないだけに、経済全体の成長力が高まっていけば、企業の支出行動が積極化していくことが期待できる。また、日本経済の成長力の高まりとともに、自然利子率が上昇すれば、日本銀行による金融緩和の効果も高まっていくと考えられる。
3.経済・物価のリスク要因
(1)経済のリスク要因
上記の中心的な経済の見通しに対する上振れないし下振れの可能性(リスク要因)としては、以下の4点がある。
第1に、海外経済の動向である。具体的には、米国のマクロ政策運営やそれが国際金融市場に及ぼす影響、保護主義的な動きの帰趨とその影響、それらも含めた新興国・資源国経済の動向、英国のEU離脱交渉の展開やその影響、地政学的リスクなどが考えられる。
第2は、2019年10月に予定される消費税率引き上げの影響である。駆け込み需要とその反動や実質所得減少の影響は、消費者マインドや雇用・所得環境、物価の動向によって変化し得る。
第3に、企業や家計の中長期的な成長期待は、少子高齢化など中長期的な課題への取組みや労働市場をはじめとする規制・制度改革の動向に加え、企業のイノベーション、雇用・所得環境などによって、上下双方向に変化する可能性がある。
第4に、財政の中長期的な持続可能性に対する信認が低下する場合、人々の将来不安の強まりやそれに伴う長期金利の上昇などを通じて、経済の下振れにつながる惧れがある。一方、財政再建の道筋に対する信認が高まり、将来不安が軽減されれば、経済が上振れる可能性もある。
(2)物価のリスク要因
以上の要因のほか、物価の上振れ、下振れをもたらす固有の要因としては、第1に、企業や家計の中長期的な予想物価上昇率の動向が挙げられる。予想物価上昇率は、先行き上昇傾向をたどるとみているが、企業の賃金・価格設定スタンスが積極化してくるまでに予想以上に時間がかかり、現実の物価が弱めの推移を続ける場合には、「適合的な期待形成」を通じて、予想物価上昇率の高まりもさらに遅れるリスクがある。
第2に、マクロ的な需給ギャップに対する価格の感応度が低い品目があることが挙げられる。公共料金や家賃などの鈍い動きが、先行きも、長期間にわたって、消費者物価上昇率の高まりを抑制する可能性がある。また、流通形態の変化や規制緩和等によって企業の競争環境が一段と厳しくなる場合には、差別化の難しい財・サービスを中心に、価格押し下げ圧力が予想以上に長く作用する可能性がある。
第3に、今後の為替相場の変動や国際商品市況の動向およびその輸入物価や国内価格への波及の状況は、上振れ・下振れ双方の要因となる。
4.金融政策運営
以上の経済・物価情勢について、「物価安定の目標」のもとで、2つの「柱」による点検を行い、先行きの金融政策運営の考え方を整理する10。
まず、第1の柱、すなわち中心的な見通しについて点検すると、消費者物価の前年比は、これまでの想定よりは時間がかかるものの、2%に向けて徐々に上昇率を高めていくと考えられる。経済・物価のリスク要因については注意深く点検していく必要があるが、2%の「物価安定の目標」に向けたモメンタムは維持されていると考えられる。これは、(1)マクロ的な需給ギャップがプラスの状態が続くもとで、企業の賃金・価格設定スタンスは次第に積極化してくるとみられること、(2)中長期的な予想物価上昇率は、横ばい圏内で推移しており、先行き、実際に価格引き上げの動きが拡がるにつれて、徐々に高まると考えられること、が背景である。
次に、第2の柱、すなわち金融政策運営の観点から重視すべきリスクについて点検すると、経済の見通しについては、2018年度はリスクは概ね上下にバランスしているが、2019年度以降は下振れリスクの方が大きい。物価の見通しについては、中長期的な予想物価上昇率の動向を中心に下振れリスクの方が大きい。より長期的な視点から金融面の不均衡について点検すると、これまでのところ、資産市場や金融機関行動において過度な期待の強気化を示す動きは観察されていない。また、低金利環境が続くもとで、金融機関収益の下押しが長期化すると、金融仲介が停滞方向に向かうリスクや金融システムが不安定化するリスクがあるが、現時点では、金融機関が充実した資本基盤を備えていることなどから、そのリスクは大きくないと判断している。
金融政策運営については、2%の「物価安定の目標」の実現を目指し、これを安定的に持続するために必要な時点まで、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続する。マネタリーベースについては、消費者物価指数(除く生鮮食品)の前年比上昇率の実績値が安定的に2%を超えるまで、拡大方針を継続する。政策金利については、2019年10月に予定されている消費税率引き上げの影響を含めた経済・物価の不確実性を踏まえ、当分の間、現在のきわめて低い長短金利の水準を維持することを想定している。今後とも、金融政策運営の観点から重視すべきリスクの点検を行うとともに、経済・物価・金融情勢を踏まえ、「物価安定の目標」に向けたモメンタムを維持するため、必要な政策の調整を行う。
以上
- 各政策委員の見通しを踏まえた経済・物価情勢の展望や金融政策運営の考え方について、7月30日、31日開催の政策委員会・金融政策決定会合で決定されたものである。 本文に戻る
- 消費税率については、2019年10月に10%に引き上げられる(軽減税率については、酒類と外食を除く飲食料品および新聞に適用される)ことを前提としている。また、現時点の情報をもとに、教育無償化政策についても織り込んでいる。 本文に戻る
- わが国の潜在成長率を、一定の手法で推計すると、「0%台後半」と計算される。ただし、潜在成長率は、推計手法や今後蓄積されていくデータにも左右される性格のものであるため、相当の幅をもってみる必要がある。 本文に戻る
- 2019年10月の消費税率の引き上げは、駆け込み需要とその反動、および実質所得の減少効果の2つの経路を通じて成長率に影響を及ぼすが、下押し効果は、2014年度の前回増税時と比べると、不確実性は大きいものの、小幅なものにとどまると予想される。 本文に戻る
- 各政策委員は、既に決定した政策を前提として、また先行きの政策運営については市場の織り込みを参考にして、見通しを作成している。具体的には、長短金利について、市場金利をもとにしつつ、展望レポートと市場参加者との物価見通しの違いを加味し、想定している。 本文に戻る
- 2019年10月に予定される消費税率の引き上げが物価に与える影響について、税率引き上げが軽減税率適用品目以外の課税品目にフル転嫁されると仮定して機械的に計算すると、2019年10月以降の消費者物価前年比(除く生鮮食品)は+1.0%ポイント押し上げられる(2019年度と2020年度の押し上げ効果は、それぞれ+0.5%ポイントとなる)。なお、教育無償化政策の影響については、統計上の取り扱いが未定ということもあり、消費者物価指数には反映されないと仮定している。 本文に戻る
- 経済・雇用情勢に比べて賃金・物価が上がりにくく時間がかかる現象は、程度に差はあるが、主要先進国に共通の現象である。この背景として、潜在的な労働供給余力の存在、世界金融危機の履歴効果、新興国を含むグローバル・サプライチェーンの深化、デジタル化を始めとする技術進歩など、多くの要因が指摘されているが、現時点で見方は収斂していない。ここでは、こうした点も踏まえつつ、長期にわたる低成長やデフレの経験といった日本特有の事情も勘案した上で、わが国の物価が弱めの動きを続けている要因を考察している。関連する詳細な分析は、今回の展望レポートの「賃金・物価に関する分析資料」(「基本的見解」と同時公表。展望レポート「背景説明」にはBOXとして掲載)参照。 本文に戻る
- わが国の消費者物価の伸び率が、新年度入り後にやや低下したことには、振れの大きい宿泊料の下落や、春先までの円高に伴うコスト上昇圧力の緩和など、短期的な要因も相応に影響している。 本文に戻る
- 中長期的な予想物価上昇率は、中央銀行の物価安定目標に収斂していく「フォワードルッキングな期待形成」と、現実の物価上昇率の影響を受ける「適合的な期待形成」の2つの要素によって形成されると考えられる。詳細は、「「量的・質的金融緩和」導入以降の経済・物価動向と政策効果についての総括的な検証」(2016年9月)参照。 本文に戻る
- 「物価安定の目標」のもとでの2つの「柱」による点検については、日本銀行「金融政策運営の枠組みのもとでの「物価安定の目標」について」(2013年1月22日)参照。 本文に戻る
参考
2018から2020年度の政策委員の大勢見通し
――対前年度比、%。なお、( )内は政策委員見通しの中央値。
| 実質GDP | 消費者物価指数 (除く生鮮食品) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費税率引き上げの影響を除くケース | |||||
| 2018年度 | +1.3から+1.5 (+1.5) |
+1.0から+1.2 (+1.1) |
|||
| 4月時点の見通し | +1.4から+1.7 (+1.6) |
+1.2から+1.3 (+1.3) |
|||
| 2019年度 | +0.7から+0.9 (+0.8) |
+1.8から+2.1 (+2.0) |
+1.3から+1.6 (+1.5) |
||
| 4月時点の見通し | +0.7から+0.9 (+0.8) |
+2.0から+2.3 (+2.3) |
+1.5から+1.8 (+1.8) |
||
| 2020年度 | +0.6から+0.9 (+0.8) |
+1.9から+2.1 (+2.1) |
+1.4から+1.6 (+1.6) |
||
| 4月時点の見通し | +0.6から+1.0 (+0.8) |
+2.0から+2.3 (+2.3) |
+1.5から+1.8 (+1.8) |
||
- (注1)「大勢見通し」は、各政策委員が最も蓋然性の高いと考える見通しの数値について、最大値と最小値を1個ずつ除いて、幅で示したものであり、その幅は、予測誤差などを踏まえた見通しの上限・下限を意味しない。
- (注2)各政策委員は、既に決定した政策を前提として、また先行きの政策運営については市場の織り込みを参考にして、上記の見通しを作成している。具体的には、長短金利について、市場金利をもとにしつつ、展望レポートと市場参加者との物価見通しの違いを加味して、想定している。
- (注3)消費税率については、2019年10月に10%に引き上げられること(軽減税率については酒類と外食を除く飲食料品および新聞に適用されること)を前提としているが、各政策委員は、消費税率引き上げの直接的な影響を除いた消費者物価の見通し計数を作成している。消費税率引き上げの直接的な影響を含む2019年度と2020年度の消費者物価の見通しは、税率引き上げが課税品目にフル転嫁されることを前提に、物価の押し上げ寄与を機械的に計算したうえで(それぞれ+0.5%ポイント)、これを政策委員の見通し計数に足し上げたものである。なお、教育無償化政策の影響については、統計上の取り扱いが未定ということもあり、消費者物価指数には反映されないと仮定している。一方、実質GDPの見通しについて、各政策委員は、現時点の情報をもとにその影響を織り込んでいる。
政策委員の経済・物価見通しとリスク評価
(1)実質GDP
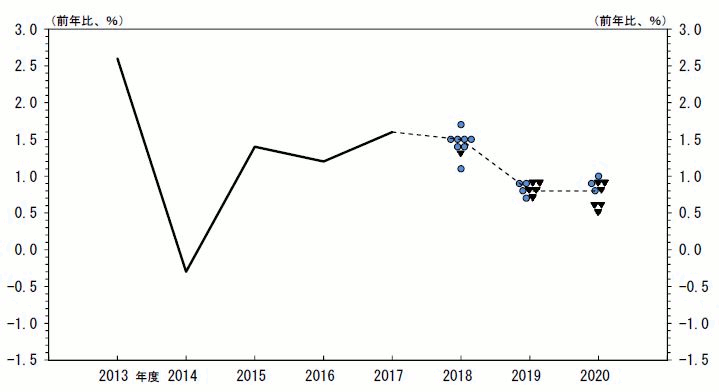
(2)消費者物価指数(除く生鮮食品)
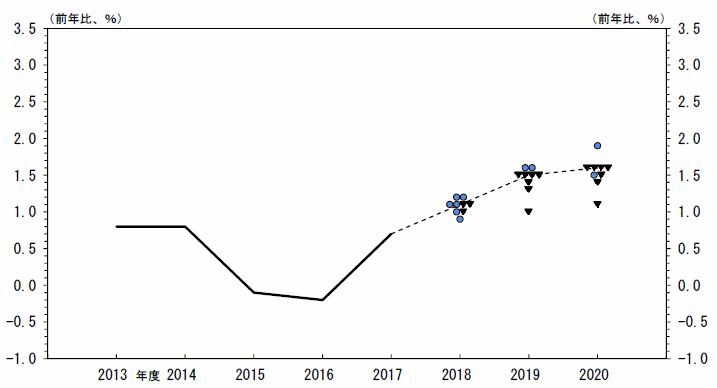
- (注1)実線は実績値、点線は政策委員見通しの中央値を示す。
- (注2)●、△、▼は、各政策委員が最も蓋然性が高いと考える見通しの数値を示すとともに、その形状で各政策委員が考えるリスクバランスを示している。●は「リスクは概ね上下にバランスしている」、△は「上振れリスクが大きい」、▼は「下振れリスクが大きい」と各政策委員が考えていることを示している。
- (注3)消費者物価指数(除く生鮮食品)は、消費税率引き上げの直接的な影響を除いたベース。
