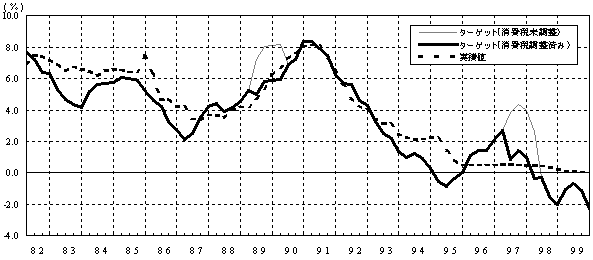ホーム > 日本銀行について > 講演・記者会見・談話 > 講演・記者会見(2010年以前の過去資料) > 講演・挨拶等 2002年 > カンサスシティ連邦準備銀行主催シンポジウム(2002年8月30日)における山口副総裁講演「変化する経済環境のもとでの金融政策」
変化する経済環境のもとでの金融政策
2002年8月30日、カンサスシティ連邦準備銀行主催シンポジウムにおける日本銀行山口副総裁講演(於 米国ワイオミング州ジャクソンホール)1
2002年10月1日
日本銀行
- 3年前のこのコンファランスにおいて、私はバブル拡大期における日本の金融政策についてお話しする機会を頂きました2。本日は、主として、バブル拡大期に続くバブル崩壊期の金融政策を振り返ることにしたいと思います。というのは、資産価格の大きな変動は、われわれにとって、もっとも切実な「経済環境の変化」であるからです。ちなみに、われわれは現在、経済が「流動性の罠」に陥るという三番目の段階にありますが、この点は将来の議論のテーマにとっておきたいと思います。
- 1今回もまた、日本銀行の同僚たち、特に翁 邦雄氏と白川方明氏との議論から有益な示唆を得た。
- 2Yutaka Yamaguchi, "Asset Prices and Monetary Policy: Japan's Experience," New Challenges for Monetary Policy, Federal Reserve Bank of Kansas City, 1999.(邦訳は、山口 泰「資産価格と金融政策 -日本の経験-」、『日本銀行調査月報』)。
- まず、少し昔の話から始めたいと思います。東京株式市場の絶頂期は、1989年末でした。しかし、不動産市場のバブルは、――日本では不動産の時価総額は株式の時価総額よりもはるかに大きいのですが――それからさらに1年ほど長く続きました。それに続いて成長率の低下が始まりました。そして、1990年代の趨勢的な成長率は年率わずかに1パーセント程度になり、1980年代の4パーセントから大幅に低下しました(図表1)。
図表1.経済成長とインフレ
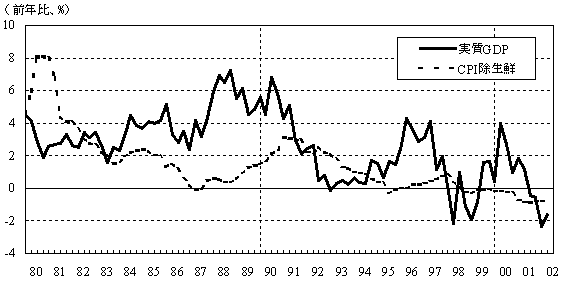
- 備考:
- CPIは消費税要因を調整済み。
- 資料:
- 総務庁、「消費者物価指数」、内閣府「国民経済計算年報」。
- こうした趨勢的な成長率の低下にバブル崩壊が大きく寄与しているのは間違いありません。しかし、それが唯一の原因とは言い切れません。もともと、日本経済は急速な高齢化や輸出主導の経済成長の限界を背景として、1980年代初頭には、より安定した成長へ移行していくことが広範に予想されていました。高成長を前提として構築された経済システムは、修正が必要とされ、実際、1980年代半ばにはすでに大きな調整期に入っていたと思われます。
- 資産価格バブルは、単に、こうした調整プロセスを中断させただけでなく、むしろ時計を逆戻りさせてしまいました。大規模な資産価格バブルの主な特徴である行き過ぎた楽観が広がり、企業は資本ストック、雇用、そして負債を積み上げました。こうしたストックの水準は経済成長が持続的に加速を続ける場合にのみつじつまが合うものでした。もともと穏やかな成長への移行が必要であった時期に逆のことが起きた結果として、バブルが崩壊したとき、それに続く調整はより苦痛に満ち、長期にわたるものとならざるを得なくなってしまいました。
日本の資産価格バブルのこうした特徴、つまりそれが1990年代における構造調整をより厳しいものにしたという点は重要であると思います。なぜなら、それは日本銀行が金融政策を運営するうえで直面した特異な環境を作り出したからです。言い換えると、 異なる環境下で運営される金融政策は、それぞれが置かれた固有の歴史的条件に照らして評価される必要がある、ということになります。従って、例えば構造的な理由から低成長へ移行する必要性がさほど無い経済の場合、金融政策の効果も日本とは当然に異なるでしょう。 - 日本銀行は1991年7月に、当時6パーセントであった公定歩合の引下げに踏み切りました。この時期は、生産の伸びや消費者物価の上昇が加速の兆候をみせ、景気上昇が峠を越えたかについて、なお、かなり大きな不確実性が存在していた時期です。それだけに持続的な資産価格デフレよりも地価バブルの再来の方が、はるかに説得的なシナリオであった時期でした。このため、1991年央の公定歩合引下げは、時期尚早な緩和として、国内外から厳しい批判を受けました。
今振り返ってみると、これを端緒として相次ぐ金利引下げが行われ、1995年9月には公定歩合は0.5パーセント――これは、ある経済学者たちが流動性の罠の臨界値であり得るとした水準です――にまで引き下げられました。約4年の間に、かなり大きかった金利引下げの余地は、事実上使い尽くされてしまったことになります。 - 日本銀行はしばしば金融緩和の遅れを批判されてきました。この点について、標準的なバックワード・ルッキング型のテイラー・ルールを評価基準として今回の金融緩和の過程を評価する研究が、日本銀行のスタッフや米国連邦準備制度のスタッフのものも含め、多数行われてきました3。図表2はその一例です。これらの研究では、バブル崩壊後の日本の金融緩和は、特に緩和がもっとも重要であった初期段階において、リアル・タイムで利用可能な金融・経済指標や市場での予測に基づく標準的な安定化政策としては概ね妥当なものであったと考えられる、と結論付けられています。しかしながら、そうした平常時には妥当とみなし得る政策対応であったにもかかわらず、趨勢的な成長率の大きな下方屈折と資産価格の急激かつ持続的な下落が生じ、それが金融システムを脆弱なものとし、経済を不安定化させてしまった訳です。
図表2.テイラー・ルール
- 備考:
-
- テイラー・ルールの定式化は以下のとおり。
基本式: Rt = r*t + π* + α x (πt - π*) + β x (Yt - Y*)
r*t: t期における均衡実質短期金利
π*: 目標インフレ率
Rt: t期における無担保コールレート(O/N物)
πt: t期におけるインフレ率(消費者物価上昇率)
Yt - Y*: t期における実質GDPギャップ
ただし、αおよびβはそれぞれ1.5、0.5の値をとる。 - 太線で示したターゲット・レートは、消費税の影響を調整している。参考まで、消費税の影響を調整していないものを細線として示している。
- テイラー・ルールの定式化は以下のとおり。
- 資料:
- 翁 邦雄・白塚重典、「資産価格バブル、物価の安定と金融政策:日本の経験」、『金融研究』第21巻第1号、日本銀行金融研究所、2002年、図表7。
- 3 例えば、日本銀行スタッフによる研究としては、白塚重典・田口博雄・森 成城、「日本におけるバブル崩壊後の調整に対する政策対応 ─中間報告─」(『金融研究』第19巻第4号、日本銀行金融研究所、2000年)、翁 邦雄・白塚重典、「資産価格バブル、物価の安定と金融政策:日本の経験」(『金融研究』第21巻第1号、日本銀行金融研究所、2002年)、また海外中央銀行、国際機関スタッフの研究としては、Alan Aherne, et al. "Preventing Deflation: Lessons from Japan's Experience in the 1990s," (International Discussion Paper No. 729, Board of Governors of the Federal Reserve System, 2002)、Bank for International Settlement, 72nd Annual Report (Bank for International Settlement, 2002)等がある。
- このようなバブル崩壊後の日本の経済パフォーマンスを眺めて、日本銀行は、名目金利の非負制約に直面する前に、標準的な安定化政策の範囲を逸脱して、より思い切った緩和を試みるべきだったとの見解も聞かれます。
こうした見解について、二つの視点から手短かに検討しておきたいと思います。最初の視点は、そうした政策の現実的な実行可能性で、これはバブル崩壊後の経済動向に関するリアルタイムでみた予見可能性に部分的に依存します。第二の視点は、資産価格バブル崩壊による弊害を緩和するうえでの思い切った金融緩和の有効性です。 - 中央銀行が「標準的な」あるいは政策ルールにそった金融政策を超える劇的な緩和策を初期段階でとったとしましょう。日本の場合であれば、一部の資産価格が急落する一方で、かなり力強い経済成長と緩やかなインフレが共存している時点での政策発動ということになりますが、それは、将来のデフレのリスクを回避するために、予めインフレを加速させておくことを意図したもの、ということになったでしょう。ここで資産価格崩壊による負のショックを相殺するために加速されるインフレ率は、インフレーション・ターゲティングを採用している国の場合であれば、通常ターゲットにするであろう水準をはるかに超えるものが必要とされるでしょう。
こうした戦略を中央銀行がとるとすれば、数年先のデフレのリスクについて、定量的な分析に裏付けられた十分な確信があり、かつそのリスクについて強い懸念を抱いている必要があります。そうした透徹した洞察力なくしては、デフレが迂遠で潜在的なリスクにしか過ぎない段階で、明示的なものか暗黙のものかにかかわらず、物価に関するターゲットを放棄することは、到底できないでしょう。 - しかし、一般的に言って、経済には不確実性が伴うため、先行きの予測はどうしても不透明なものにならざるを得ません。特にバブル崩壊後の局面では、経済情勢の読みを難しくする特殊な問題として、資産市場の動向に関する大きな不確実性があります。
第1に、私たちは資産市場がどう展開し、実体経済との均衡がどこで回復されるのか確信をもつことができません。さらに、日本における1990年の株式市場と不動産市場の動向のように、資産の種類によって価格変動は異なるパターンをとり得ます。こうした資産ごとに区々の価格変動は、バブル時代の慣性としての希望的観測が尾を引き、期待形成に撹乱的な影響を及ぼすバブル崩壊の初期段階に特に生じ易いものです。このため、キャピタル・ロスの規模についての見込みや、それが企業・家計の財務的な健全性に対して与える悪影響を予測することは極めて困難になります。 - 第2に、資産価格から実体経済および物価動向への波及メカニズムに関しても不確実性が存在します。例えば金融仲介において銀行が中心的な役割を果たす日本のような経済では(図表3)、キャピタル・ロスは銀行システムに徐々に蓄積される傾向があります。実際、日本ではショックは金融部門に封じ込められるので、実体経済には波及しないという見方がありました。このため、地価がいずれ回復に転じるまで持ち堪えられれば経済情勢は好転する筈との信念は、かなり広汎に共有されていました。しかし、銀行の自己資本が危機的な境を越えて劣化するに及んで、急激な信用逼迫が発生してしまいました。こうした不確実性の高い環境のもとで、経済予測は、企業・家計、そして特に銀行のバランスシートの悪化による「向い風」が生じるタイミングやその程度を織り込まなければ正確を期すことができません。
図表3.企業の金融負債構造と家計の金融資産構造
(1999年12月末残高ベース)[1]企業の金融負債構成(金融負債合計に占める割合)
![[1]企業の金融負債構成(金融負債合計に占める割合) 単位:% 日本 米国 ドイツ 借入 38.8 12.1 33.3 債券 9.3 8.2 1.3 株式・出資金 33.8 66.6 54.3 貿易・企業間用等 18.1 13.0 11.0](./img/ko0210a3.gif)
[2]家計の金融資産構成(金融資産合計に占める割合)
![[2]家計の金融資産構成(金融資産合計に占める割合) 単位:% 日本 米国 ドイツ 現金・預金 54.0 9.6 35.2 債券 5.3 9.5 10.1 投資信託 2.3 10.9 10.5 株式・出資金 8.1 37.3 16.8 保険・年金準備金 26.4 30.5 26.4 その他 3.9 2.2 1.1](./img/ko0210a4.gif)
- 資料:
- 日本銀行調査統計局、「資金循環統計からみた我が国の金融構造」、『日本銀行調査月報』12月号、日本銀行情報サービス局、2000年
- 次に、二つめの視点、つまり仮想的な早期緩和の効果に移りたいと思います。いくつかのシミュレーションによれば、こうした政策をとれば、インフレ率が将来のデフレに対する十分な緩衝材として機能する水準まで押し上げられたであろうという結果になっています(図表4)。
ここで重要な点は、日本の経済・金融システムの苦境の根底にあるものは何か、という点です。確かに、名目金利の非負制約のもとでは、たとえデフレが現在の日本で見られるように年1パーセントに満たない程度のものであったとしても、デフレの分だけ実質金利は押し上げられてしまいます。しかしながら、図表5に示されているように、資産価格デフレは、過去10年近くの間、年率10パーセント近いペースで続いており、若干プラスの実質金利がもたらすよりもはるかに大きな重荷として経済活動に作用してきた可能性が高いと思われます。図表4.仮想的な早期金融緩和に関するシミュレーション
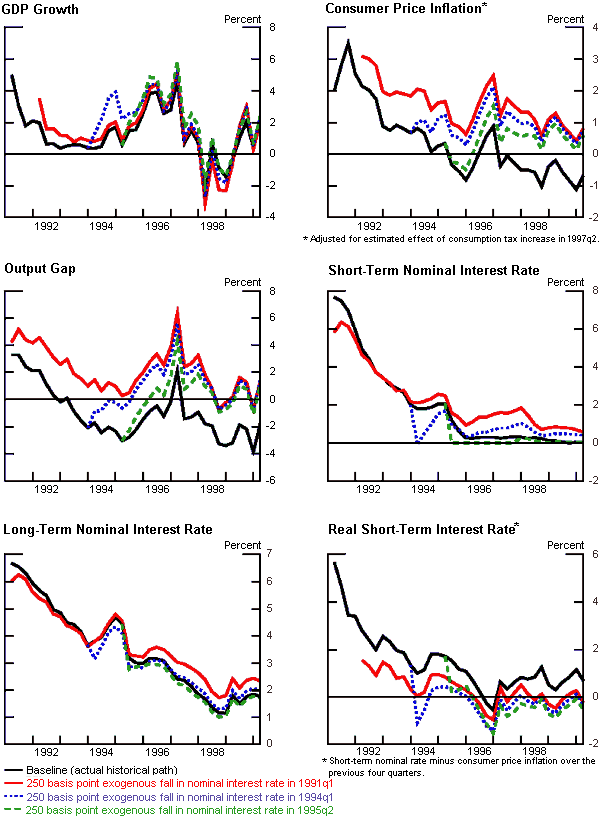
- 資料:
- Alan Aherne, et al. "Preventing Deflation: Lessons from Japan's Experience in the 1990s," International Discussion Paper No. 729, Board of Governors of the Federal Reserve System, 2002, Exhibit IV.2.
図表5.資産価格デフレ
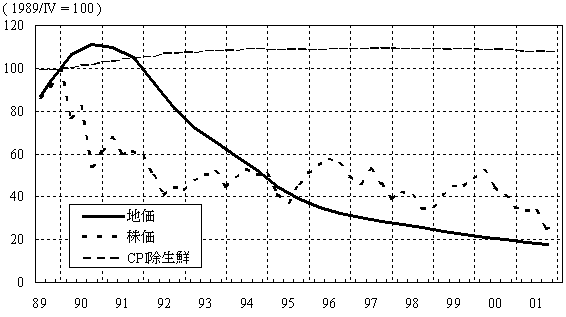
- 資料:
- 日本銀行「金融経済統計月報」、総務庁「消費者物価指数」、日本不動産研究所「市街地価格指数」。
- 私にとっての疑問は、一体、思い切った緩和策によって、不動産価格の下落、ひいてはバランスシート問題が顕著に緩和され得たのだろうか、という点にあります。一般的には、大幅な金利低下は、GDPギャップを縮小させ、インフレ率を上昇させます。そして資産価格が下落しているときは、その下落を緩和させることにも役立つはずです。日本の資産価格バブルの後に、思い切った緩和を行うことで、そうした結果が達成され得たでしょうか。私はそれには懐疑的です。
われわれは、資産インフレが大規模なバブルに発展してしまった後では、市場を「軟着陸」させることは不可能であることを、これまでも繰り返し目の当たりにしてきました。もしそうであるならば、そして、もし問題になっている資産市場が、日本の不動産市場のように、伝統的に金融安定のある種のアンカーとして機能してきたものであるとするなら、金融政策が需要やインフレを喚起する能力は、必然的に著しく損なわれてしまうでしょう。資産市場を軟着陸させるという戦略がたとえ成功したとしても、資産価格と経済ファンダメンタルズの間の不可避的な調整を先送りするだけだったかもしれません。 - バブル崩壊後の動向を予測する中央銀行の能力が完全ではないとすれば、バブルが拡大していると見なされるに至ったときに思い切った引き締め策をとることこそ、今一度、検討してみるべきなのでしょうか。この問題は、私が3年前にここでお話したことです。その時と同様、私は依然としてこの点についても懐疑的なままです。しかしながら、バブル崩壊に先行して生じている大規模な信用供与こそが、ひとたび潮の流れが反転すると価値のないものとなり、当事者のバランスシートを著しく毀損するのが常であるという事実を踏まえると、資産市場が上げ潮にのっているときに、「過度な」信用供与を抑えるために可能な方策を模索していくことは意味があることではないか、と思います(日本の信用量と資産価格の動きについては図表6を参照)。
図表6.実質総合資産価格と信用量
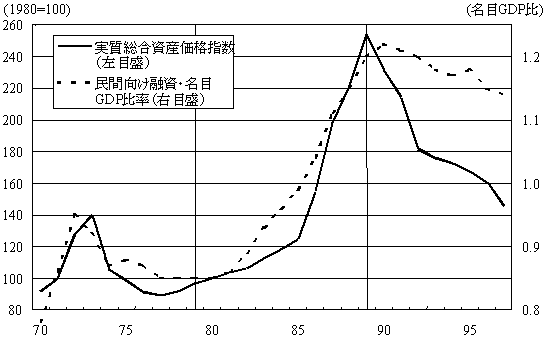
- 備考:
- 実質総合資産価格指数は、株式および住宅・不動産価格を消費者物価指数で実質化したうえで加重平均したもの。ウエイトは、民間部門の資産残高構成比より算出。
- 資料:
- Bank for International Settlements, Quarterly Review, International Banking and Financial Market Developments, August 1999
- 最後に、もう少し視野を広げて所見をいくつか付け加えることで、話の結びとさせて頂きたいと思います。これまでのトラックレコードが示しているように(図表1、図表2)、日本銀行は1980年代から1990年代初めにかけて、あたかもテイラー・ルールのような政策ルールに則ったようにみえる政策運営を行ってきました。しかし、それにもかかわらず、もっとも激しい資産市場の変動に見舞われました。また、資産価格の上昇局面だけでなく下落局面においても、日本銀行は、こうした政策ルールにそった経路から逸脱して政策を運営すべきであったという批評がなされています。私の目からみると、政策ルールの議論がより意味のあるものでかつ頑健なものとなるためには、少なくとも大規模な資産価格の変動を考慮にいれる必要があるように思います。われわれの経験によれば、物価の安定により低金利が実現したもとで、将来に対する行き過ぎた楽観が生じてくると、それらの組み合わせは資産価格バブルへの道を開くことになり得る、ということを示しているからです。
- 最後に、バブル崩壊期の経済動向において、もっとも重要な点は、失われた資本の規模とその分布、つまり、経済システムの中でだれが損失を負担するのかということだと思います。日本においては、資本の毀損規模は圧倒的に大きく、また、銀行部門に集中していました。
経済が日本のような規模で資本を失うという状況に直面したとき、問題を早期に解決するうえで決定的に重要なのは、金融インフラの役割、それがうまく機能するかどうかです。この文脈におけるインフラとは、適切な会計制度、情報公開、規律あるガバナンス、インセンティブ・メカニズム、そして監督といったものを含みます。日本は、こうした枠組みを発展させ、組み込む、という面で時間がかかりました。
私はこの点を強調しておきたいと思います。なぜなら、もし、キャピタル・ロス全般、なかんずく銀行システムのキャピタル・ロスの処理について、迅速かつ強力な進展が図られていたとすれば、日本の金融政策は、異なる環境のもとで運営されたことになったかもしれないからです。アンカーとなる資産価格の崩落といった重大なショックのさ中では、金融政策とプルーデンス政策を関連づけて対処することの必要性は、いくら強調しても強調し過ぎることはないと思います。