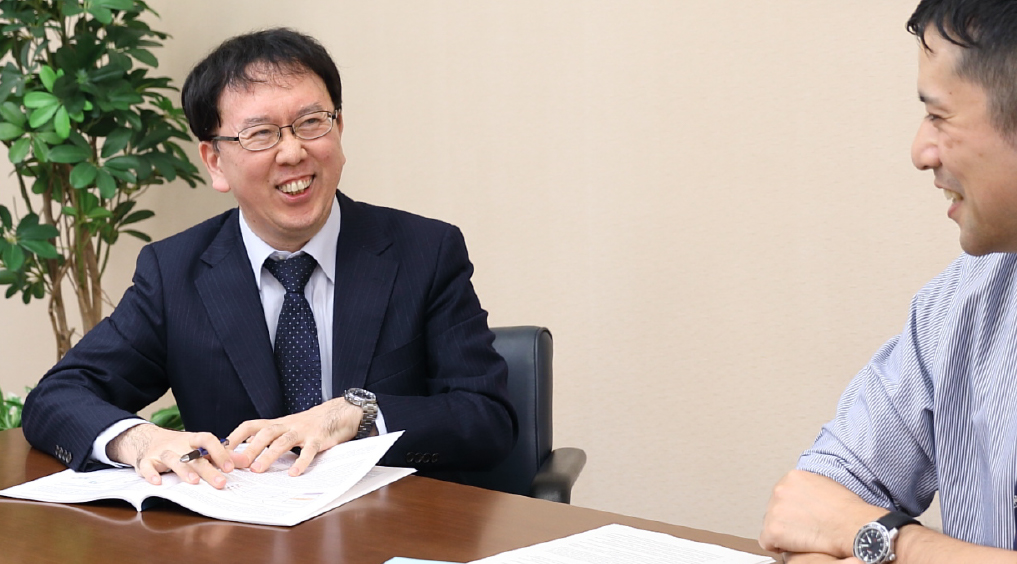トップページ キャリア採用行員紹介【総合職】 小林 俊のページです。
【総合職】小林 俊
【総合職】小林 俊
金融機構局 国際課長 (現 新潟支店長)
2006年2月 金融機構局入行
2010年7月 金融市場局
2013年6月 金融機構局
2017年6月 金融市場局
2019年6月 金融機構局
日本銀行で働く前の民間銀行、中央官庁、公的金融機関での10年間
私は、大学(経済学部)を卒業後、民間銀行に就職し、社会人としての一歩を踏み出しました。その当時の私の考えは、「私的利益の追求/公益への奉仕」、「実務経験の蓄積/アカデミックな貢献」という2つの座標軸で、同時に追求することは必ずしも容易ではない4つの分野で、螺旋を描くようにキャリアを積み重ねていきたいということでした。民間銀行では、営業、企画、リスク管理など幅広く実務の経験が積めたほか、努力して獲得した手数料収益等がそのままボーナスに反映されることの満足感もありました。また、銀行に在籍したまま中央官庁に出向する機会があり、その際、政府白書の執筆や環境関連の情報開示枠組みの検討作業に携わり、パブリックな仕事のやりがいを実感する貴重な経験をしました。そんなある時、最初の就職時に考えていた4つの分野のうち、「アカデミックな貢献」がこのままでは欠けていると感じました。そこで、思い切って民間銀行を退職し、大学院(修士、博士後期課程)に進みました。そこでは金融工学を学び、論文を執筆して学会で発表する、また、中途採用で入った公的金融機関でリスク管理の仕事に知識を活かす、という日々を過ごしました。30代前半の頃です。
日本銀行での15年間の経験
そうした折、縁があって、日本銀行で働く機会を頂きました。日本銀行への就職を検討した際、最大の決め手は、社会人になった当初に思い描いた4分野のうち、「公益への奉仕」、「実務経験の蓄積」、「アカデミックな貢献」という3つが同時に実現できるのではないか、という期待でした。実際働いてみたところ、期待通りでした。現在、日本銀行での勤務は15年を超え、その間、金融機構局では、金融安定に関するリサーチや国際金融規制の制度設計、金融市場局では、国内外の金融市場のモニタリングや市場統計の作成といった様々な仕事に携わり、実務の幅を大きく広げることができました。また、これまで、「コストと便益のバランスが取れた金融規制の枠組みはどのようなものか」、「非伝統的金融政策は市場機能にどのような影響を与えるか」といったテーマを含む8本の対外公表論文の執筆や金融システムレポートの編集、これらの多くについては学会でも報告を行うなど、知的刺激に満ちたリサーチ活動も行えました。そして、何よりも、日々、金融機関や金融市場の参加者、あるいは会社の同僚との間で、公益について考え ─ 例えば、あるべき国際金融規制=公共財の姿はどのようなものか、金融政策を実行する上で市場とどのように向き合うか ─、議論をしながら進める仕事は、非常にやりがいがあるものでした。このように、「公益への奉仕」、「実務経験の蓄積」、「アカデミックな貢献」という3つの要素が同時に追求できる仕事に携われることは、とても幸せなことだと感じています。
現在取り組んでいる仕事 ─ 世界の金融システム安定への貢献
現在、私は、金融機構局国際課という部署で仕事をしています。国際課の主な役割は、バーゼル銀行監督委員会等の国際会議への参加を通じ、グローバルな金融機関の規制・監督のルールの策定と実施に貢献していくことです。2007年以降の世界金融危機を経て、金融規制の強化が必要との声が強まり、各国間の調整を積み重ねて2017年に最終化されたバーゼルⅢという新たな枠組み ─ 自己資本比率規制の強化や流動性規制等の新規導入 ─ がここ10年間の大きな成果です。ただ、バーゼルⅢの着実な実施が大事、と考えていた矢先に襲ってきたコロナ禍への対応を含め、足もとでは、新たな課題が次々と浮上してきています。例えば、取引が拡大している暗号資産を金融規制上どのように位置づけるか、多様化している金融機関へのサイバー攻撃にどう備えるか、金融業界として気候問題にどのように対応していくべきか等です。リスク管理の実務、金融工学や環境問題の知識など日本銀行に勤務する前の経験をベースに、この15年間の中央銀行業務で得た知識・経験を加味し、今後も引き続き、新たな課題に向き合い、社会に貢献できればと考えています。
キャリア採用行員紹介INDEXへ
次へ