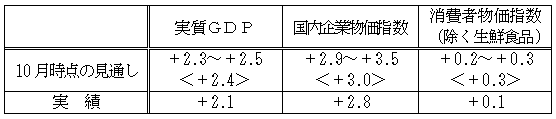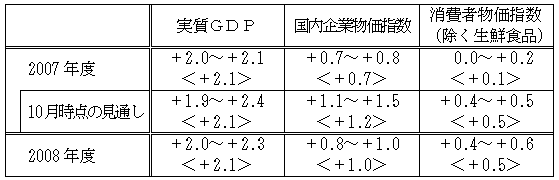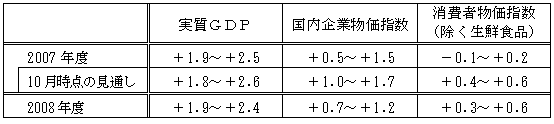経済・物価情勢の展望(2007年4月)
2007年4月27日
日本銀行
【基本的見解】 1
(経済・物価情勢の見通し)
わが国経済は、緩やかに拡大している。好調な企業部門に比べると、家計部門の改善テンポがやや緩慢であるが、全体としてみれば、2006年度の経済は、前回(2006年10月)の「経済・物価情勢の展望」(展望レポート)で示した見通しに概ね沿って推移したとみられる 2。
先行き2007年度から2008年度を展望すると、生産・所得・支出の好循環メカニズムが維持されるもとで、息の長い拡大を続けると予想される。成長率の水準は、2007年度、2008年度とも、潜在成長率を幾分上回る2%程度で推移する可能性が高い。
こうした先行きの経済の姿は、以下のような前提やメカニズムに基づいている。第1に、海外経済の拡大が続くことを背景に、輸出は増加を続けると予想される。米国経済は、足もとは住宅市場の調整が続いていることなどから減速しているが、先行きは安定成長へ軟着陸する可能性が高い。海外経済全体としても、地域的な拡がりを伴って拡大を続けると想定される。第2に、企業部門の好調が続くとみられる。高水準の企業収益が続く中で、設備投資は増加を続けると予想される。もっとも、企業が投資採算を厳しく見定める姿勢を堅持していることを踏まえると、資本ストック循環の観点からみて、設備投資の伸び率は次第に低下していくと考えられる。第3に、好調な企業部門から家計部門への波及が、緩やかながら着実に進んでいくとみられる。グローバルな競争や資本市場からの規律の高まりを意識した企業の人件費抑制姿勢は続くとみられるが、雇用者数の増加が続く中で、労働市場の需給がさらに引き締まっていけば、賃金の上昇圧力は徐々に高まっていくと想定される。加えて、株式配当の増加など様々なルートを通じて、企業部門の好調は家計部門に波及し、そうしたもとで、個人消費は緩やかな増加基調を辿る可能性が高い。第4に、極めて緩和的な金融環境が引き続き民間需要を後押しするとみられる。金融機関は、積極的な貸出姿勢を続けており、短期金利は、経済や物価との関係からみて、極めて低い水準で推移している。
こうした経済の見通しのもとで、物価を巡る環境をみると、第1に、設備や労働といった資源の稼働状況は高まっており、今後もさらに高まっていくとみられる。マクロ的な需給ギャップをみても、引き続き、需要超過方向で推移していくと考えられる。第2に、ユニット・レーバー・コスト(生産1単位当たりの人件費)は、なお低下を続けているものの、賃金の緩やかな上昇のもとで、下げ止まりから若干の上昇に転じていく可能性が高い。第3に、民間経済主体のインフレ予想は、各種調査では、既往の石油製品価格の下落の影響などから全般に下振れているが、引き続き先行きにかけて物価が緩やかに上昇していく形となっている。
物価指数に即してみると、2006年度の国内企業物価指数は、国際商品市況の下落を背景に、前回の見通し対比幾分下振れて推移している。先行きについては、原油などの商品市況や為替相場にも左右されるが、上昇基調を続けるとみられる。
消費者物価指数(除く生鮮食品)は、足もとは、原油価格下落などの影響もあって前回見通し対比幾分下振れている。先行きは、原油価格の動向にもよるが、前年比でみて目先はゼロ%近傍で推移する可能性が高いものの、より長い目でみると、プラス幅が次第に拡大するとみられる。その結果、2007年度はごく小幅のプラス、2008年度は0%台半ばの伸び率となると予想される。
(上振れ・下振れ要因)
以上述べた見通しは、前述の前提やメカニズムに依拠した上で、最も蓋然性が高いと判断される見通しについて述べたものである。したがって、先行きの経済情勢については、以下のような上振れまたは下振れの要因があることに留意する必要がある。
第1に、海外経済の動向である。米国では、住宅市場の調整は続いているが、これまでのところ、個人消費が堅調に推移するなど、経済に広範な影響を及ぼしていない。また、設備投資は、このところ先行指標の一部が弱い動きとなっているが、高水準の企業収益を背景に、緩やかな増加基調が維持されるとみられる。しかし、住宅市場の調整が予想以上に深いものとなったり、設備投資が下振れた場合、景気は一段と減速する可能性がある。また、物価情勢については、設備や労働といった資源の稼働状況が高水準であるもとで、原油価格の動向などと相俟って、インフレ圧力が減衰しない可能性もある。この場合、金融市場の反応等を通じて、米国経済や世界経済全体に悪影響が及ぶリスクがある。中国では、力強い拡大が続いているが、固定資産投資や輸出の動向次第では、見通し期間中の成長率が上振れる可能性がある。また、原油価格をはじめとする国際商品市況も、その状況如何では、世界経済の先行きに影響を与える可能性がある。
第2に、IT関連財の需給動向である。IT関連財の国内における在庫増は、主として国内向け製品に関する局所的な要因によるものとみられ、世界全体でみたIT関連財の需要は着実に拡大基調を続けていると考えられる。ただし、世界的な供給拡大のペースが速いだけに、海外経済の減速などから需要予測が大きく下方修正されれば、需給バランスが崩れる可能性もある。もっとも、その場合でも、収益力や財務基盤などの面で、わが国企業部門の体力が高まっていることは、景気全体への影響の緩衝材になると考えられる。
第3に、金融環境などに関する楽観的な想定に基づく、金融・経済活動の振幅の拡大である。企業や金融機関などの財務面での改善が進む中、実質金利が極めて低い水準にあることから、金融・経済活動が積極化しやすい環境にある。また、大都市で地価の上昇傾向が明確化してきているなど、資産価格の動きも、そうした行動を活発化させる方向に作用すると考えられる。こうした中で、仮に、期待成長率や資金調達コスト、為替相場や資産価格の見通しなど、先行きの採算に関する楽観的な想定に基づいて金融・経済活動が積極化する場合には、金融資本市場において行き過ぎたポジションが構築されたり、非効率な経済活動に資金やその他の資源が使われ、長い目でみた資源配分に歪みが生じるおそれがある。このような行動は、短期的には景気や資産価格を押し上げることがあっても、その後の調整を余儀なくされ、息の長い成長を阻害する可能性がある。
次に、物価上昇率の先行きについても、上振れ・下振れ両方向の不確実性があることに留意する必要がある。第1に、需給ギャップに対する物価の感応度は、経済のグローバル化の進展や規制緩和などを背景に低下しているとみられるが、その程度には不確実性がある。とりわけ、景気拡大が続く中にあっても、賃金の上昇テンポが生産性との対比で高まっていかないような場合には、物価への下押し圧力が根強く残ることが考えられる。一方、今後、設備や労働といった資源の稼働状況が緩やかながらさらに高まっていく過程で、インフレ予想や企業の人件費抑制スタンスが大きく変化し、物価に上振れ圧力が加わる可能性もある。第2に、地政学リスクなどを背景に、原油をはじめとする商品市況の動向には上下両方向に不確実性が大きい。
(金融政策運営)
日本銀行は、「中長期的な物価安定の理解」(金融政策運営に当たり、各政策委員が、中長期的にみて物価が安定していると理解する物価上昇率)を念頭に置いた上で、経済・物価情勢について2つの「柱」による点検を行い、先行きの金融政策運営の考え方を整理することとしている。
「中長期的な物価安定の理解」は、消費者物価指数の前年比で0〜2%程度の範囲内にあり、委員毎の中心値は、大勢として、概ね1%の前後で分散している(BOX参照)。
第1の柱、すなわち先行き2008年度までの経済・物価情勢について最も蓋然性が高いと判断される見通しについて、政策金利に関して市場金利に織り込まれている金利観を参考にしつつ点検すると、上述した通り、わが国経済は、生産・所得・支出の好循環メカニズムが維持されるもとで、息の長い拡大が続くとみられる。また、消費者物価指数(除く生鮮食品)の前年比は、目先はゼロ%近傍で推移する可能性が高いが、より長い目でみると、プラス幅が次第に拡大していくと予想される。こうした動きは、「中長期的な物価安定の理解」に沿ったものと評価できる。このように、わが国経済は、物価安定のもとでの持続的な成長を実現していく可能性が高いと判断される。
第2の柱、すなわち、より長期的な視点を踏まえつつ、確率は高くなくとも発生した場合に生じるコストも意識しながら、金融政策運営の観点から重視すべきリスクを点検すると、経済・物価情勢の改善が展望できる状況下、金融政策面からの刺激効果は一段と強まる可能性がある。例えば、仮に低金利が経済・物価情勢と離れて長く継続するという期待が定着するような場合には、企業や金融機関などの行き過ぎた活動を通じて、中長期的にみて、経済・物価の振幅が大きくなったり、非効率な資源配分につながるリスクがある。一方、前述のような下振れ要因が発生した場合、経済情勢の改善が足踏みするような局面が考えられる。また、経済情勢の改善にもかかわらず、物価が上昇しない状況が続く可能性もある。ただし、企業部門の体力や金融システムの頑健性が高まっていることから、物価下落と景気悪化の悪循環が生じるリスクはさらに小さくなっていると考えられる。
昨年3月の量的緩和政策解除以降の金融政策運営を振り返ると、経済・物価情勢の先行きを展望して、(1)生産・所得・支出の好循環メカニズムが働き、息の長い成長が続く中で、(2)消費者物価は長い目でみると緩やかに上昇し「中長期的な物価安定の理解」に沿って推移する蓋然性が高いという判断に基づいて、経済・物価情勢の変化に応じて、徐々に金利水準の調整を行ってきた。物価上昇圧力が弱いもとで、調整のペースはゆっくりとしたものであり、極めて低い金利水準による緩和的な金融環境が維持された。今後の金融政策運営においても、こうした基本的な考え方を維持する方針である。すなわち、「中長期的な物価安定の理解」に照らして、日本経済が物価安定のもとでの持続的な成長軌道を辿る蓋然性が高いことを確認し、リスク要因を点検しながら、経済・物価情勢の改善の度合いに応じたペースで、徐々に金利水準の調整を行うことになると考えられる。
- 4月27日開催の政策委員会・金融政策決定会合で決定されたものである。
- なお、2006年度の成長率は、昨年12月にGDP統計の2005年度計数が確報化により下方修正されたことに伴い、2006年度への発射台(年度中の各期の前期比伸び率がゼロであった場合の年度平均の前年比)が0.3%ポイント縮小したことの影響を受けた。
以上
(BOX)「中長期的な物価安定の理解」の点検
日本銀行は、昨年3月に「『物価の安定』についての考え方」を公表し、その中で、「中長期的な物価安定の理解」(金融政策運営に当たり、中長期的にみて物価が安定していると各政策委員が理解する物価上昇率)について、原則としてほぼ1年毎に点検していくこととしていた。今回、概ね1年を経過したことから、点検を実施した。
そのポイントは以下の3点である。
(1)物価の安定についての基本的な考え方の再確認
「『物価の安定』についての考え方」で示した以下の点など、基本的な考え方が再確認された。
(1)「物価の安定」とは、家計や企業等の様々な経済主体が物価水準の変動に煩わされることなく、消費や投資などの経済活動にかかる意思決定を行うことができる状況であること。
(2)金融政策の効果が波及するには長い期間を要し、また、様々なショックに伴う物価の短期的な変動をすべて吸収しようとすると経済の変動がかえって大きくなることから、十分長い先行きの経済・物価の動向を予測しながら、中長期的にみて「物価の安定」を実現するように努めていくこと。
(2)「中長期的な物価安定の理解」の検討の視点
「中長期的な物価安定の理解」の検討に当たっては、(1)消費者物価指数の計測誤差(バイアス)、(2)物価下落と景気悪化の悪循環のリスクに備えた「のりしろ」、(3)物価が安定していると家計や企業が考える物価上昇率、を考慮した。この点、バイアスは、昨年の基準改定を踏まえても、引き続き、大きくないと判断される。「のりしろ」に関しては、企業部門の体力や金融システムの頑健性が高まっていることから、物価下落と景気悪化の悪循環が生じるリスクはさらに小さくなっていると考えられる。また、物価上昇率の変動が小さい中で、物価が安定していると家計や企業が考える物価上昇率には、大きな変化はないとみられる。
(3)「中長期的な物価安定の理解」の点検結果
以上の議論を踏まえ、「中長期的な物価安定の理解」は以下の通りとなった。
「中長期的な物価安定の理解」は、消費者物価指数の前年比で0〜2%程度の範囲内にあり、委員毎の中心値は、大勢として、概ね1%の前後で分散している。
参考
▽2006年度の政策委員の大勢見通し 3と実績
対前年度比、%。なお、< >内は政策委員見通しの中央値。
▽2007〜2008年度の政策委員の大勢見通し 3,4
対前年度比、%。なお、< >内は政策委員見通しの中央値。
- (注1)2006年度の実質GDPの「実績」については、1〜3月期の計数を前期比横這いと仮定して計算した推定値。
- (注2)各政策委員は、政策金利について市場金利に織り込まれたとみられる市場参加者の予想を参考にしつつ、上記の見通しを作成している。
- 3「大勢見通し」は、各政策委員が最も蓋然性の高いと考える見通しの数値について、最大値と最小値を1個ずつ除いて、幅で示したものであり、その幅は、予測誤差などを踏まえた見通しの上限・下限を意味しない。
- 4政策委員全員の見通しの幅は下表の通りである。
対前年度比、%。