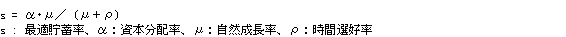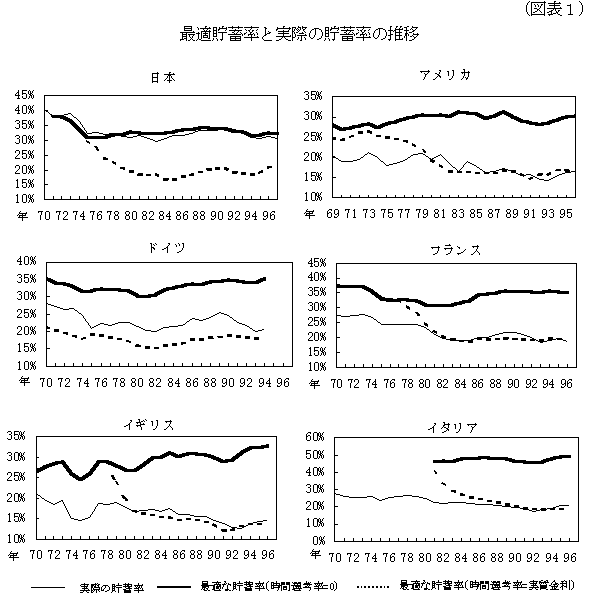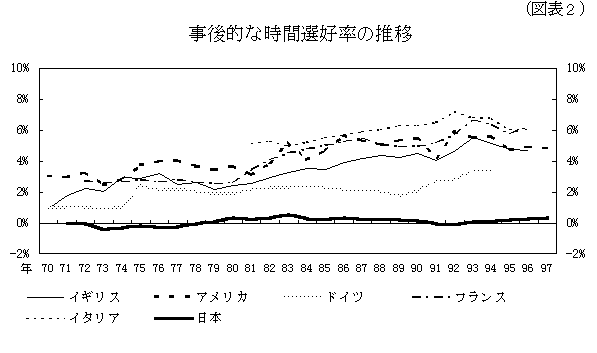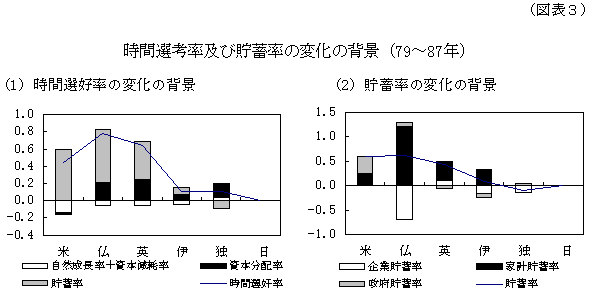日本の貯蓄は過剰なのか:あるいは欧米主要国の貯蓄が過少なのか
修正黄金律の観点からみた主要国貯蓄率の分析
1999年12月
大山剛
吉田孝太郎
日本銀行から
日本銀行調査統計局ワーキングペーパーシリーズは、調査統計局スタッフおよび外部研究者の研究成果をとりまとめたもので、内外の研究機関、研究者等の有識者から幅広くコメントを頂戴することを意図しています。ただし、論文の中で示された内容や意見は、日本銀行あるいは調査統計局の公式見解を示すものではありません。
なお、ワーキングペーパーシリーズに対するご意見・ご質問や、掲載ファイルに関するお問い合わせは、論文の執筆者までお寄せ下さい。
以下には、(要旨)を掲載しています。全文は、こちら (cwp99j05.pdf 332KB) から入手できます。
要旨
本稿の問題意識と目的
我が国の過剰貯蓄が問題視されて久しい。その背景には、貯蓄投資バランスが経常収支を決定するとの考え方に基づき、我が国の膨大な経常収支黒字額が、他国に類をみない高い貯蓄率によってもたらされているとの見方がある。また近年の長期に亘る不況が、部分的にせよ、消費の不振(貯蓄の過剰)によってもたらされているという事実も、過剰貯蓄議論をサポートする材料となっている。
しかしながら、一国の貯蓄率が過剰か否かは、単に経常収支の絶対額や他国との比較のみから論じることは出来ない。貯蓄とは、基本的には投資を通じて"将来の消費"に繋がるものである。したがって、人々は本来、現在の消費のみではなく、"将来に亘る消費"から得られる効用を最大化するよう行動しているはずである。 このように考えれば、貯蓄することに伴い現在の消費を我慢する苦痛のコストが、貯蓄によって将来もたらされる消費の効用を上回れば、現在の貯蓄率は過剰だといえる。 何故なら、この場合、現在の消費を増やして、将来の消費(貯蓄)を減らした方が、一生涯に受けられる効用は増えるからである。こうした考え方は、経済学における経済成長論の中で「修正黄金律」として理論化されており、この中で「最適貯蓄率」は、中長期に亘り消費から得られる効用を最大化させる貯蓄率と定義される1。
この最適貯蓄率は、基本的には、(1)これまでの貯蓄(=投資)から得られるリターン(具体的指標としては、こうした所得が全所得に占める比率<資本分配率>)と、(2)社会全体が現在の消費を将来に先延ばしすることをどれほど苦痛に感じるかの程度(時間選好率)によって決定される2。例えば、資本分配率=20%、貯蓄率=30%という状況が続いている社会を想定しよう。この社会は明らかに過剰貯蓄だといえる。何故なら、所得の3割を貯蓄することで、この分現在の消費を犠牲にする一方、これまでの投資から得られる所得は、全体の2割に過ぎないからである。新規投資が十分な収益を生み出せないという意味では、過剰資本の状態とも言えるわけで、この場合、現在の消費を増やし、貯蓄(=投資)を減らした方が、一生涯の消費から得られる効用は増えることとなる。
一方、資本分配率が同じであっても、A国とB国で、時間選好率が異なれば、最適貯蓄率も異なってくる。例えば、A国の国民は、勤労期の我慢を美徳とし、老後のため(ないしは子孫のため)の貯蓄をそれほど苦としない(時間選好率が低い)一方、B国の国民は、いわゆる「宵越しの金をもたない」タイプ(現在の消費を出来るだけ増やす=時間選好率が高い)だとしよう。この場合、人々が得る将来の消費(貯蓄)量が同じでも、A国とB国で、人々がそこから得る効用は異なる(A国>B国)ため、当然最適貯蓄率も A国がB国よりも高くなる。
本稿の目的は、以上のような修正黄金律の考え方に基づいた場合、我が国の貯蓄が過剰だといえるのか、あるいは、むしろ欧米主要国の貯蓄が過少なのか、を確かめることにある。 具体的には、先行研究が示唆する「時間選好率」を前提とした最適貯蓄率が、実際の貯蓄率からどの程度乖離しているかをみる。次に、仮に実際の貯蓄率が常に最適貯蓄率と等しいと仮定した場合に、そこから事後的に決まる時間選好率の変化が、何らかの合理的な理由で説明できるか否かを考える(仮に、説明できなければ、過剰ないしは過少貯蓄が生じている可能性が高い)。
- なお、この最適貯蓄率の概念は、単に家計部門のみならず、政府や企業部門まで含めた国民貯蓄率(以下、単に貯蓄率と呼ぶこととする)が対象である点には留意する必要がある。
- 修正黄金律に基づく最適貯蓄率は、次のように表すことが出来る。
分析結果の要約
本稿の分析結果を、予め要約すると、次の通りである。
- (1)我が国の貯蓄率は、時間選好率をゼロと仮定した場合3、最適貯蓄率に近くなるものの、時間選好率として実質金利を用いると、大幅な過剰貯蓄となる。一方、ドイツを除く欧米主要国では、70年代後半以降、時間選好率として実質金利を用いたケースで、実際の貯蓄率と最適貯蓄率が近くなる一方、時間選好率をゼロとすると過少貯蓄となる(図表1)。
- (2)仮に人々が合理的であり、実際の貯蓄率は最適貯蓄率と常に等しいと仮定した場合に、事後的に求められる時間選好率をみると、日本、ドイツ(ドイツ統合以前)では、長期間に亘り低く、しかも安定した状況が続いている。一方、米国を含むその他主要国では、実質長期金利の上昇と歩調を合わせるように、時間選好率は70年代末から急速に上昇している(図表2)。
- (3)なお投資率に関し、実際の投資率=最適投資率と仮定した上で求めた事後的な時間選好率をみると、資本移動の自由化が進んだ80年代以降、貯蓄率のそれに比べ国際的に収斂する傾向がみられる。このように、欧米主要国(ドイツを除く)における70年代末以降の時間選好率の上昇は、日本、ドイツの貯蓄率には殆ど影響を与えなかった一方、資本の自由化を通じて、日本、ドイツの投資率を押える方向で作用した可能性が考えられる。この結果、両国では投資率が貯蓄率を下回る状況(=経常収支黒字の発生)、また米国等では、それとは逆の状況(=経常収支赤字の発生)を恒常化させることとなった。
- (4)日本、ドイツ以外の諸国で、事後的に求めた時間選好率が70年代末以降上昇した背景をみると、
欧州諸国(ドイツを除く)では、資本分配率の上昇とともに、家計貯蓄率の低下が、一方、米国、カナダでは、主に政府部門及び家計部門の貯蓄率低下が時間選好率上昇に対応している4(図表3)。
- (5)以上の背景に関し、まず欧州諸国についてみると、資本分配率の上昇は、70年代における労働生産性の伸びを上回る賃金上昇の反動の結果として、ドイツを含む欧州主要国全てでみられた。一方、資本分配率の上昇は、この間投資家の機関投資家化や資本市場の自由化・グローバル化に伴い資本収益率に対する上昇圧力が増した結果、企業の投資率上昇には結びつかず、むしろ投資家への資本所得還元を増やした。
特に、家計の保有資産に占める株式、投信等の比率が高いドイツ以外の欧州諸国では、企業部門より格段に時間選好率が高いと考えられる家計部門への資本所得還元を増やしたと考えられる。 - (6)こうした資本所得は、配当という形で直接的に家計所得を増やすというよりは、企業内に内部留保として止まり、資産価格の上昇という形で間接的に家計所得に還元される傾向が強かった。もっとも、現行SNA下では、キャピタル・ゲインは所得に付加されないため、キャピタル・ゲインを当てにした消費の増加は貯蓄率の低下となって現われ、この結果、ドイツ以外の欧州諸国では、この間家計貯蓄率が低下したと考えられる(これに対しドイツでは、家計資産に占める株式・投信等の比率が低く、この結果、家計貯蓄率に与える影響も小さかった)。換言すれば、 欧州諸国(ドイツを除く)では、資本分配率が上昇する(資本所得全体のパイの増加)中で、時間選好率の高い家計部門が、企業部門の資本所得を自らの所得として強く意識するようになり、これが企業の投資を抑える一方、家計の消費を促す状況(=マクロ経済の時間選好率上昇)を招いたと考えられる。
- (7)一方日本では、我が国固有の資本市場構造が当時まだ根強く残っていたこともあり、海外からの資本収益率上昇圧力が弱かったほか、家計資産に占める株式・投信等の比率も概ね低い水準に止まっていたため、時間選好率は安定的に推移したと考えられる。
- (8)米国では、この間、様々な要因から家計貯蓄率の低下がみられたが、特徴的なのは、同時に政府貯蓄率の低下も生じた点である。
一方、我が国でも近年政府貯蓄率は急速に低下する傾向にあるが、これがマクロ全体の貯蓄率低下をもたらすまでには至っていない。我が国では、歴史的に、家計貯蓄率と政府貯蓄率の間に逆相関の関係がある程度確認できるが、90年代以降については、家計貯蓄率が所得を巡る不確実性の増大から上昇する中にあって、消費不振等に起因する不況対策として政府支出が増大し、政府貯蓄率が一段と悪化したことが、こうした関係を強めた可能性が高い。 - (9)このように、従来みられた我が国の高貯蓄率は、長期間に亘る成長の極大化という観点からは決して過剰とはいえなかった。但し、その安定性に関しては、(i)欧米諸国が70年代以降経験してきた資本市場やコーポレート・ガバナンスの変化の到来が単に遅かった、及び(ii)我が国の家計貯蓄率が、所得を巡る不確実性の増大から上昇する局面では、政府支出の拡大(政府貯蓄率の低下)により、貯蓄率の一層の上昇(最終需要の一層の減少)に歯止めを掛けることが出来た、等の特殊事情に負う面が大きいように思われる。
今後について考えると、我が国においても、資本市場のグローバル化に伴い投資家の要求収益率が今後徐々に高まると同時に、家計保有資産に占める投信・株式等の比重が上昇していけば、80年代の欧州でみられたように、企業の投資が抑えられる一方で、家計の消費が促されていく(=マクロ経済の貯蓄率低下)可能性は十分考えられる。また政府貯蓄率も、今後義務的経費の比率が一層高まる中で、仮に経済が今後回復に向かったとしても、現状の大幅な財政赤字幅が速やかに縮小するとは考えにくい。こうした中、経常収支と裏腹な関係にある貯蓄投資バランスは、投資率が貯蓄率と同じテンポで減少する限り大きな変化はない。但し、(3)でも指摘したとおり、これまでは、主に投資率のみが欧米主要国の時間選好率上昇からの影響を受け、結果的に恒常的な経常収支黒字とバランスしてきたが、今後こうした影響は貯蓄率にも及ぶと考えられるほか、政府貯蓄率の改善も早急には期待できないと考えれば、これまで続いて来た大幅な貯蓄超過(経常収支黒字)も、今後そのGDPに占める比率は低下していく可能性も考えられる。
- 3仮に現在の世代が、未来永劫の将来世代の効用まで勘案して消費を決定するのであれば、時間選好率はゼロとなる。
- 4時間選好率は、資本分配率一定の下で、実際の貯蓄率が低下すれば上昇する。何故なら、投資から得られるリターンが変化しない中で、貯蓄(=投資)が減少するということは、時間選好率(消費先延ばしの苦痛)が高まったことを意味するからである。また、実際の貯蓄率一定の下で、資本分配率が上昇すれば、時間選好率は上昇する。これは、投資から得られるリターンが高まっているにもかかわらず、貯蓄(=投資)が高まらないということは、時間選好率が高まったためと考えられるからである。