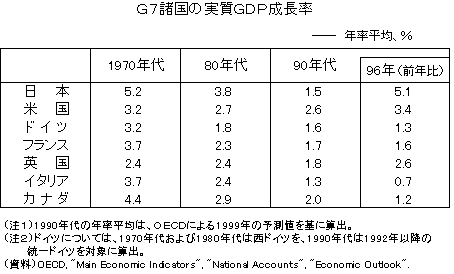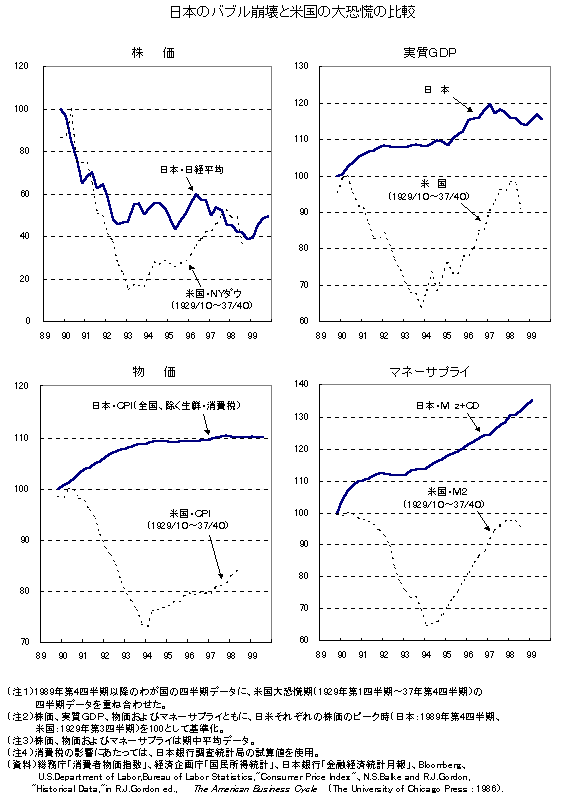金融政策は構造政策までは代替できない
(『週刊ダイヤモンド』(2000年1月29日号)への寄稿)
2000年 1月31日
白川方明
近年、日本の金融政策の運営スタンスをめぐって、相反するふたつの政策論が展開されている。第一の議論は景気が停滞している以上、できることはなんでもやるべきであり、金融政策についても効果の大きさはともかく、さらなる緩和を進めるべきだという議論である。第二の議論は、日本経済に必要なことは構造改革であり、金融政策の発動余地はないという議論である。両者の相対的な影響度は足許の景気に対する悲観、楽観の程度に応じて変わってきたが、本稿では以上のような議論を念頭に置きながら、金融政策の役割を含め、日本経済が本格的な成長軌道に復帰するために何が必要であるかを考えてみたい(注)。
- (注)「金融政策と構造政策:日本の経験」(日本銀行調査月報1999年11月号)参照。
最初に、議論の出発点として、日本経済の「失われた10年」の背景を考えてみよう。表が示すように、日本はG7諸国の中で1990年代の実質GDP成長率は二番目に低く、80年代と比較した成長率の低下幅はもっとも大きかった。この最大の理由としては80年代後半から90年代初にかけてのバブルの発生と崩壊が挙げられることが多い。しかし、日本とほぼ同規模の大きなバブルと銀行危機を経験したスウェーデンはその後株価のピークを更新し現在は経済成長軌道に復帰している。バブルの発生と崩壊は非常に重要な要因であったが、これだけで90年代における日本経済の停滞を説明することは不十分である。
金融政策でできることとできないこと
それでは、金融政策は日本経済の停滞をもたらした要因であったであろうか。短期金利は90年代初の8%台から現在は実質ゼロまで引き下げられてきたが、それにもかかわらず、この間のマネー・サプライの伸び率は25%、年率で2.5%という低い伸びにとどまっており、現在も前年比3%程度の伸びである。マネー・サプライ増加の中身にも、経済の停滞の特質が反映されている。上述のマネー・サプライの増加率に対応した金融機関の資産増加率の内訳を見ると、民間向け貸出しの増加率は6%にとどまっており、政府向け信用の増加率(62%)を大幅に下回っている。マネー・サプライは日本銀行の金利引下げに金融機関が自動的に反応して増加するものではなく、金融機関が信用創造活動(企業の借入れ計画を審査して貸出しを行なったり有価証券に投資を行なうこと)を行なうことによってはじめて増加するものである。上述の政府向け信用と民間向け貸出しのコントラストは、金融機関にとって、自らのリスクテイク能力を前提とすると、採算性の高い貸出機会が多くなかったことを端的に物語っている。
いずれにせよ、この数年間の金融政策は、積極的な金融緩和論者が90年代前半に「積極的に金融緩和を行なえば景気は回復する」と主張した際に想定していた金融政策スタンスそのもの、あるいはそれをはるかに上回る緩和スタンスではなかろうか。それにもかかわらず、90年代の金融緩和は日本経済を成長軌道に復帰させるほどには強力な効果を発揮しなかった。しかし、このことは金融政策が無力であったことを意味するものではない。金融政策はある意味では非常に強力であった。というのも、未曾有のバブル崩壊後、日本経済は何回かデフレ・スパイラルの危険に直面したが、短期金利を思い切って引き下げることによって、デフレ・スパイラルに陥ることだけはなんとか回避しえたからである。この点は、今回の日本の長期にわたる景気停滞を米国の1930年代の大恐慌と比較するとよくわかる。株価の下落幅は両者ともそれほど大きな違いはないが、物価や実質GDP、マネー・サプライの動きは明らかに異なっている(下図参照)。
日本経済を成長軌道に復帰させるだけの効果を持ちえなかったという点では、財政政策も同様であった。日本の一般政府の財政バランスは91年には2.9%の黒字であったが、OECDによれば99年にはOECD諸国の中で最悪の8.7%の赤字になり、政府債務残高の対GDP比も120%近くまで上昇することが見込まれている。言い換えれば、財政政策も金融政策も、マクロ経済学の教科書に照らせばこれ以上は考えられないといったレベルまで積極化している。それにもかわらず、現在程度の経済の状態であるということは、90年代の日本経済の停滞は景気循環の問題としてだけでなく、潜在的な経済成長能力低下の問題としてもとらえる必要があることを意味している。
経済成長の鍵は社会全体としての変化への対応能力
潜在的な経済成長能力は何によって決まるのであろうか。潜在的な経済成長能力は、労働や資本といった計測可能な生産要素の増加とそれ以外の要因によってもたらされる生産性(全要素生産性、total factor productivity)の上昇によって規定されるが、特に重要なのは生産性の上昇である。「生産性」というと、テクニカルな響きがあるが、筆者なりに解釈すると、(全要素)生産性とはさまざまな変化に対する社会全体としての不断の対応能力が表象化されたものである。
変化の原因は技術革新かもしれないし、財・サービスの相対価格の変化かもしれないし、さらにマクロ経済的なショックかもしれない。原因はなんであれ、企業はさまざまな変化に対応して、あるいは変化を見越して、新しい商品やサービスを開発したり、生産・販売の方法を見直すことが必要になる。その際、税制、法律、会計、規制等の「制度」は企業にとって所与である。そうした制度が硬直的であれば、企業の変化への対応は阻害される。
その意味で、公的当局には制度の見直しという大きな責任があり、不断の変化への対応が求められるという点では民間企業と同様である。言い換えれば、持続的な経済成長を遂げられるかどうかは、社会全体としてさまざまな変化に対応しうるメカニズムをどの程度備えているかに大きく依存している。
90年代の日本経済の停滞にはそうした意味での社会全体としての対応能力の低下も影響している。その一例として、不良債権問題の解決がなぜ遅れたかを考えてみたい。この点については、金融機関経営のレベルで言えば、先行きの景気や地価の回復に期待した経営姿勢が挙げられる。ある時点まで不良債権の償却や引当ての自由度が乏しかったことも関係している。そしてなによりも、公的資金の投入や金融機関の破綻処理法制の整備が遅れたこと、さらに、これらの要因の背後にあるより根源的な理由として、多額の不良債権がマクロ経済に及ぼす深刻な影響についてなかなか理解が得られなかったことが挙げられる。
もちろん金融機関が破綻した場合のシステミック・リスクという概念自体は抽象的には理解されていたが、どちらかと言うと、金融機関や金融市場内部の問題としてとらえられる傾向があり、マクロ経済の問題としては十分には認識されていなかった。
97年秋に三洋証券や山一証券、北海道拓殖銀行などが相次いで破綻し急激な信用収縮を経験してはじめて、不良債権問題はマクロ経済に深刻な影響を及ぼす問題であるということが実感として認識されるようになった。そうしたことがもっと早く理解されていたならば、公的資金の投入も破綻処理法制の整備ももう少し早く実現し、その結果、金融システムの健全化を通じて経済全体のリスクテイク能力も早く回復していたかもしれない。
「問題の発見・解決能力」の勝負
このことは社会全体の対応能力という観点から、ふたつの教訓を提示している。第一は、市場メカニズムの重要性である。日本の金融機関に経営戦略の本格的な見直しを促した直接的なきっかけはジャパン・プレミアムをはじめとするグローバルな金融・資本市場からの圧力であった。もちろん、市場には「行き過ぎ」は付き物である。しかし、問題が大きければ大きいほど、企業にとっても、社会全体にとっても、市場による圧力なしに自らに変化を促すことはむずかしい。
第二は、社会全体としての「問題の発見・解決能力」の重要性である。市場メカニズムは強力ではあるが、民間経済主体の行動は所与の制度やマクロ経済環境の下での競争である。もちろん、法律、税制、会計、規制等の制度が社会的コストの大きいものであれば長期的には見直されていくであろうが、重要なことは見直しのスピードである。経済・金融がグローバル化した今日、「社会的コストの高い制度」を維持した場合のマクロ経済への影響は致命的である。 この点で、バブル以降の経験が示すように、経済の成長・発展を阻害するリスクや構造要因の存在や性格を早く認識し、具体的な解決策を提示し、解決を求めていく努力が極めて重要であることを示している。そうした努力は企業、大学等についても求められているが、特に公的当局は専門家として果たすべき役割が大きい。
政府債務管理の重要性
それでは、「問題を発見し解決する」という観点から見た場合、現在日本が具体的に意識すべき問題はなんであろうか。この点では、例えば、急速な人口高齢化、政府債務の大幅な増加、国際的に見て高水準の政府投資等が日本の構造問題としてしばしば指摘されている。本稿ではこれらの問題とも関連するが、増大を続ける日本の政府債務の管理の重要性を指摘したい。前述のように、現在日本の政府債務の対GDP比率は国際的に見ても際立った高水準である。この点に関しては、しばしば日本の個人貯蓄率の高さが引用されるが、個人の貯蓄は決して「徴用」できるものではなく、それ自体で安心材料になるわけではない。というのも、税率の引上げは政治的に限界があるだけでなく、海外への経済活動のシフトを含めサプライサイドに悪影響を及ぼし、税収の増加にはつながらない可能性が高いからである。時折議論される「調整インフレ」も、わが国が終戦直後のような統制経済であるならともかく、発達した資本市場が存在する下では将来の利払い債務の増加をもたらすことになる。結局、政府の債務状況を改善するためには、市場原理を重視した経済改革が基本となる。そのためには、政府の活動を適切に評価しうるメカニズムも必要である。公共投資であれ、外為市場への介入であれ、政府の活動には当然ファイナンスを伴うが、一国全体として債務の状況や政府活動のコストを正確に認識しうる体制を整備することは債務管理の前提条件である。
政府債務管理という点では、政府債務を削減するという量的な問題だけでなく、国債市場の改革も重要である。国債は単に政府の資金調達手段であるだけでなく、さまざまな金融商品のプライシングのベンチマークやヘッジ手段としても重要である。経済が安定的に発展するためには健全な銀行システムと資本市場の両方が不可欠であるが、流動性の高い国債市場は社債市場の発達のためにも不可欠である。昨年は国債市場においてもさまざまな改革措置が講じられ、いくつかの点で状況は改善したが、懸案のひとつである国債市場への非居住者の参入の増加についてはあまり改善されていない。
中央銀行の役割
問題を発見し解決する能力は中央銀行にも求められる。この面で日本銀行が果たすべき第一の役割は経済が全体として上振れ、下振れ両方向にどのようなリスクを抱えているかを分析し、説明することである。リスクはさまざまであるが、例えば、地価の下落がまだ止まっていないことは意識すべきリスクのひとつである。ゼロ金利という異例の金融政策が経済全体にどのようなリスクをもたらしているかも十分意識しておく必要がある。その場合、短期的なリスクも重要であるが、より重要なのは中長期的なリスクへの洞察である。というのも、バブルの発生にしても崩壊にしても、80年代後半以降の経験から得られる最大の教訓は、金融政策は中長期的なリスクを十分意識して予防的に運営する必要があるという点に求められるからである。近年、金融政策の教科書の内容は大きく書き換えられてきた。以前の教科書では、金融政策は「経済の状況に合わせて調整する」ことに主眼が置かれていたが、近年は「経済や金融の安定的な環境を提供する」ことに主眼が置かれている。その場合、金融政策は現在まだ顕在化していないリスクを理由に金融政策を運営することになるだけに、中央銀行の説明はわかりにくく時として不人気なものとなりやすいが、説明を行なうことは独立した中央銀行の義務であり責任である。
第二の役割は、中央銀行の業務を市場の変化に応じて見直していくことである。例えば、日本銀行は現在、資金や国債の決済のRTGS化(即時決済)に取り組んでいる。金融調節に当たっては、昨年四月に公募入札が始まった政府短期証券を使った買いオペをはじめ、さまざまな見直しを行なっている。金融機関に与信を行なう際に受け入れる担保の面でも、昨年は資産担保証券の受入れを開始するとともに、担保の審査の方法についても改善を図っている。中央銀行の提供するサービスも「制度」のひとつであり、市場の変化に応じて中央銀行の業務を見直していくことは、構造改革を支える意味をもつものである。
変化の兆し
持続的な経済成長能力を高めるという観点から最近の日本の状況を見た場合、ベーシックなレベルでいくつかのポジティブな動きが見られ始めている。例えば、公的当局による政策の説明は格段に増えてきている。また、政策提案を行なう際にパブリック・コメントを求めることも徐々に導入され始めている。さらに、公的当局の活動に関する会計やディスクロージャーへの関心も高まりつつある。これらは望ましい公共政策のあり方を考えるための知的インフラを整備するという点で明るい動きであり、問題の発見・解決能力の向上につながりうる動きである。また、実体経済の面でも、米国に比べ水準は低いとはいえ、最近日本への対内直接投資が増加していることに象徴されるように、戦略的な合併、買収、企業分割等、企業経営は急速に変化している。
冒頭の金融政策の役割に関する議論に戻ると、金融政策は必要な調整を行なうまでの「時間を買う」ことはできるかもしれない。しかし、金融政策は構造改革までは代替しえない。現在日本に求められていることは、持続的な経済成長を可能にするさまざまな構造改革であり、社会全体としての問題を発見し解決を図っていく仕組みではなかろうか。
(文中、意見にわたる部分は筆者の個人的な見解であり、筆者の属する日本銀行の見解ではない)
日本銀行から
日本銀行金融市場局ワーキングペーパーシリーズは、金融市場局スタッフ等による調査・研究成果をとりまとめたもので、金融市場参加者、学界、研究機関などの関連する方々から幅広くコメントを頂戴することを意図しています。ただし、
論文の内容や意見は、執筆者個人に属し、日本銀行あるいは金融市場局の公式見解を示すものではありません。
なお、ワーキングペーパーシリーズに対するご意見・ご質問や、掲載ファイルに対するお問合せは、論文の執筆者までお寄せ下さい。