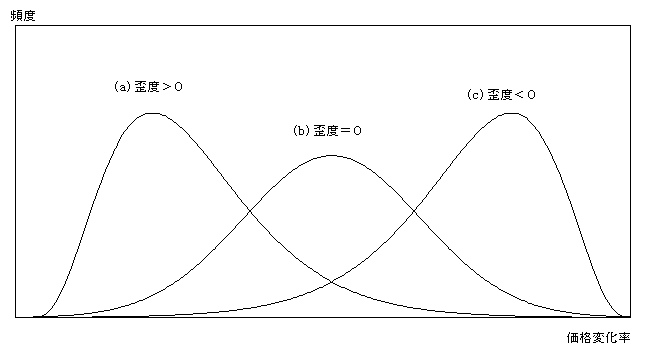Downward Price Rigidity of the Japanese CPI
-----Analysis by Probability Density Functions and Spatial Density Functions
(CPIの下方硬直性の検討)
1999年 8月
粕谷宗久
日本銀行から
日本銀行調査統計局ワーキングペーパーシリーズは、調査統計局スタッフおよび外部研究者の研究成果をとりまとめたもので、内外の研究機関、研究者等の有識者から幅広くコメントを頂戴することを意図しています。ただし、論文の中で示された内容や意見は、日本銀行あるいは調査統計局の公式見解を示すものではありません。
なお、ワーキングペーパーシリーズに対するご意見・ご質問や、掲載ファイルに関するお問い合わせは、論文の執筆者までお寄せ下さい。
以下には、(日本語要旨)を掲載しています。
1.目的
本稿の目的は、価格の下方硬直性を「価格上昇時よりも下落時の変化のテンポが遅い状態」と定義した上で、CPIの個別品目について、下方硬直性の有無を統計的に検証することにある。
一般に、財・サービスの価格に下方硬直性があるとすれば、それは賃金の硬直性のよるものであれ、制度的要因によるものであれ、個別品目レベルの問題と考えられる。しかし、CPI全体といった集計量に関しては、例えば多くの品目価格が下落する一方、一部の個別品目価格が大きく上昇する場合などに、見掛けの下方硬直性が観測されてしまう可能性がある。こうした観点から、以下では個別品目レベルに時系列的な統計手法を用いることによって、どのような品目に下方硬直性が存在するのかを確かめることとする。
2.分析方法
本分析の基本的なアイデアは、価格に下方硬直性がある場合、価格変化率の分布に正の歪度が生じるという点にある。ここで歪度とは、次図に示されているように、分布の歪み具合いを表わす指標であり、分布の右裾が長ければ正の値をとり(a)、左裾が長ければ負の値をとる(c)。したがって、「価格上昇時よりも下落時の変化のテンポが遅い状態」という意味で価格に下方硬直性がある場合には、価格変化率が一定水準以下に低下しにくく、その水準周辺に分布が集中する結果、分布は(a)のように右裾が長い形となり、歪度は正の値を取る筈だからである。
具体的には、CPIを構成する個別品目の時系列データ(全580品目のうちデータが連続でない等の品目を除く558品目)について、図のような価格変化率の分布図を作成した。その上で、各分布図について歪度を算出し、有意に「歪み」があると検定された品目をピックアップすることによって、下方硬直性を有する品目を特定化した。
なお、分布図の作成および歪度の検定にあたっては、データの非定常性の可能性から生ずるバイアスを調整している。つまり、Phillips(1998,1999)で提案された新たな2つの方法(定常性をチェックするためのより精度の高い検定法、および非定常データのための密度関数<分布図>推計法)を活用し、時系列が定常か非定常かを峻別したうえで、各々に適した分布図推計と歪度検定を行っている。
価格変化率の分布の歪度に関する概念図
3.分析結果
CPI(除く生鮮食料品)のウエイトでみると、約2−3割の品目に下方硬直性が認められた。品目種類別内訳をみると、主として、住居、光熱・水道、運輸・通信、教育、一部の食料(国産米、学校給食など)等に下方硬直性が検出された。
昨年中のマイナス成長によって、マクロの需給ギャップは大幅に拡大しているとみられるにもかかわらず、このところCPI(除く生鮮食料品)は前年比ゼロ近傍で推移しているが、その背後にも、上記のようなCPIの下方硬直性が一部影響している可能性が考えられる。
以上