日本銀行の金融調節の枠組み
(本文その2)
3.金融調節の実務的枠組み
前述のように、金融調節上の誘導対象である無担保コール翌日物金利は、主として資金の需要と供給の関係で決まるものと考えられます。本章では、翌日物金利に影響する資金の「需要」と「供給」がどのような要因で決まるかについて整理します。
(1)金融調節で調整する「資金」
前述のとおり、金融調節とは、ターゲット金利の適切な誘導を目的とした、市場における資金量の調整を言いますが、「資金」という用語は色々な意味で使われますので、ここで用語の意味を明確化しておきます。
金融調節で調整する資金とは、民間金融機関が日本銀行に開設している日銀当座預金(金融機関サイドからみると日銀預け金)の残高を言います。日銀当座預金残高の内訳をみますと、(a)預金取扱金融機関が、法律に基づいて行う準備預金の積み立て額(準備預金残高)が、大きな部分を占めています。(b)また、日本では、預金取扱金融機関以外の金融機関(証券会社、証券金融会社、短資会社等)も、日銀当座預金を開設しており、資金決済ニーズなどに応じて残高が発生します。本稿では、とくに断らない限り、(a)(b)の双方を含む民間金融機関の日銀当座預金全体の残高に対する需要を「資金需要」と言い、金融調節により供給される日銀当座預金残高を「資金供給」と言います。
(2)金融調節による翌日物金利誘導の仕組み
A.民間金融機関相互間の日銀当座預金残高の調整
民間金融機関は、企業や家計などの顧客からの要求払い預金の引き出し請求等にいつでも応じる義務を負っているほか、顧客からの依頼に応じて為替送金等を行っています。こうした預金および決済サービスを円滑に提供するために、民間金融機関は、日本銀行の当座預金に十分な資金を保有しています。このような様々な金融業務の遂行に伴い、個々の民間金融機関の日銀当座預金残高は、日々変動します。民間金融機関は、このような日々の日銀当座預金残高に生じる余剰や不足を、短期金融市場、とりわけ取引の約定当日に資金授受が可能なコール市場における資金取引を通じて相互に調整します7。資金の授受は、通常、金融機関が日本銀行に開設した日銀当座預金の資金振替によって行われます。仮に、A行に適正な日銀当座預金残高の水準に比べて10億円の余剰、B行に同額の不足があれば、A行がB行にコール資金の放出を行い(B行からみればコール資金の調達)、日銀当座預金の資金振替が行われれば、過不足の調整ができます(図表1参照)。このような日銀当座預金残高の相互調整は、実際には、民間金融機関全体で行われています。
- 7 短期金融市場には、コール市場以外にも、ユーロ円預金取引市場、短期国債市場、国債レポ市場、CD市場、CP市場等様々な市場が存在しますが、これらの市場では約定の翌日または翌々日に資金授受を行う先日付スタートの取引が多く、即日スタートの資金取引はコール取引が中心です。
<図表1>コール取引を通じた銀行間の資金余剰・不足の調整
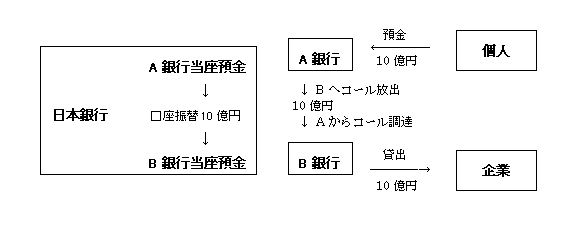
B.金融調節によるマクロ的な日銀当座預金残高の調整
民間金融機関にとっての適正な日銀当座預金残高は、資金決済ニーズや法定準備保有ニーズなどにより決まります。ある日の民間金融機関全体の資金需要に対し、十分な残高が日銀当座預金に存在している場合には、コール市場を通じて民間金融機関相互間の資金過不足調整が可能であり、日本銀行の出番はありません。しかしながら、何らかの外的要因――銀行券や財政資金の動きに左右されます(後述)――により、民間金融機関全体の日銀当座預金残高が減少(増加)する場合には、いくら金融機関相互間で調整しても、資金需要に比べて、民間金融機関全体として日銀当座預金残高の不足(余剰)の発生が避けられません。この結果、そのままでは翌日物金利に上昇(低下)圧力が働きます。ここで、日本銀行が、金融調節による資金供給の量を多め(少なめ)にすれば、翌日物金利の上昇(低下)圧力は弱まり、金利上昇(低下)を防ぐことができます。このように、資金需要の状況や日銀当座預金残高全体の増減要因の動きを勘案して、金融調節による資金供給量を調整するのが、翌日物金利誘導の基本的な仕組みです。
(3)翌日物金利に影響する要因:その1――資金需要
先に述べたように、中央銀行による資金供給が、資金需要に比して多めか少なめかによって、翌日物金利に低下・上昇圧力が生じます。以下では、まず、資金需要――民間金融機関全体の日銀当座預金残高に対する需要――の決定要因について説明します。
A.法定準備需要
わが国では、民間の預金取扱金融機関8に対し、預金などの対象債務の額に所定の比率を乗じた金額(法定準備需要)以上の資金を、「準備預金」として、日銀当座預金残高で保有することを法律で義務づけています。準備預金の保有は、1か月間(毎月16日から翌月15日まで<積み期間>)の日々の日銀当座預金残高の合計値(積数)が法定所要額を上回るように行えばよく、毎日一定額以上の残高を保有する必要はありません9。金融機関は、積み期間を通して、法定所要額以上の資金残高を確保しようとする一方、準備預金には付利されないので、法定所要額を上回る金額(超過準備額)を極力小さくし、法定所要額を充足するギリギリの水準に日銀当座預金残高を調整しようとします。なお、2000年1月積み期における1日当たりの法定所要準備額は、3.9兆円です。
上述のように、金融機関は毎日一定額の準備預金残高を持っていなければならないという訳ではなく、「積み期間」を通じて法定所要額を満たせばよいこととなっています。このため、金融機関には先行きの金利動向を勘案しながら、自らの積立額を調整し得る余地があります。例えば、仮に積み期間中の金利水準が一定の場合は、金融機関はどのタイミングで準備預金を積んでもコストは変わりません。しかしながら、市場参加者の間で、積み期間中に金利水準が上昇(低下)する可能性が高いとの見方が強まった場合には、各金融機関が準備預金の積みコストを抑制しようとして、極力積みの進捗を早める(遅らせる)結果、現時点での準備需要が強まり(弱まり)、翌日物金利に上昇(低下)圧力がかかります。このように、市場参加者の金利観も、法定準備の積みペースを通じて翌日物金利に影響を与えます。なお、民間金融機関が、法定準備需要を充足するために日銀当座預金に保有する資金残高は、次項で述べる資金決済需要を満たすためにも使うことが可能です。
- 8 準備預金制度の対象金融機関は、「銀行法」上の銀行、「長期信用銀行法」上の長期信用銀行、信用金庫(預金残高が1,600億円超の先)、農林中央金庫と定められています。
- 9 極論すれば、積み期間のどこか1日だけ法定準備額全額を積み上げ、残りの期間をゼロとするような積み方も可能です。
B.資金決済需要
民間金融機関は、前述のとおり、銀行業務遂行に伴って発生する日々の資金決済需要を満たすためにも、必要な日銀当座預金残高を保有しようとします。ただ、わが国の場合、現状では、準備預金制度に基づく法定所要額の1日当たりの平均金額(平均所要準備額)が、通常時における日々の資金決済に必要な当座預金残高を上回っていることが多いと考えられる10ため、民間金融機関は、それぞれの平均所要準備額を基準に自己の当座預金残高を調整する傾向があります。しかし、5・10日(ごとう日)11、決算期末など、手形や小切手等の資金決済額が通常より大きくなる日においては、平均所要準備額と同程度の当座預金残高では、資金決済需要を充足できない可能性があります。とくに、日本のコール市場の場合、13時(交換尻時点)を資金決済時点とする取引のウエイトが70%程度を占めていることから、その資金決済額が大きくなる日には、大手金融機関は1日の決済終了時点(17時頃)ではなく、日中の13時の時点で、十分な当座預金残高を確保しようとします12。このような繁忙日には、それまでの準備預金の積みが順調であっても、資金決済需要の強まりを主因に、翌日物金利が上昇することもあります。こうしたケースでは、通常は法定準備需要を下回っている資金決済需要が、法定準備需要を上回るため、資金需要に対して、より強い影響を及ぼすことになります。
なお、市場参加者の流動性リスクに関する見方の変化も、資金決済需要に影響します。流動性リスクとは、例えば預金が突然大量に引き出されたような場合に、金融機関がコール等の資金市場で十分な資金(流動性)を調達できないリスクです。流動性リスク不安は、銀行の不良資産問題の悪化など金融システム不安の強まりから生じることがあります。例えば、1997年から98年にかけて、わが国では大手銀行や証券会社の経営破綻が相次ぎ、金融システム不安が増大しました。この局面では、万一の預金解約等に備えて、民間金融機関が法定準備需要を上回る日銀当座預金残高を確保する傾向が強まり、金利上昇圧力が増大しがちでした。
また、流動性リスク不安は、何らかの事情で市場全体の資金決済リスクに関する懸念が増大したり、市場取引が著しく不活発になるなど、市場機能が大きく低下するおそれが強まることによっても生じます。例えば、最近ではコンピューター2000年問題の影響が典型です。昨年末にかけて、多くの金融機関は、コンピューターの誤作動に伴う資金決済リスクの顕現化に備え、昨年末の当座預金残高を例年より大幅に積み増しました。
このような場合、日本銀行が法定所要額や通常の資金決済需要のみを勘案して資金供給するだけでは、資金需要が十分に満たされないことになります。
- 10 これは、現行の準備預金制度や準備率、および日銀当座預金を通じた決済システムの仕組みなどの下で成立している現象であり、これらの制度・システムや金融環境が変化すれば、資金決済需要が恒常的に法定準備需要を上回ることもあり得ます。
- 11 毎月5日、10日、15日、20日、25日、月末日を総称して、「5・10日」と言います。
- 12 日銀当座預金を通じた資金決済は、現在では、殆どが特定の決済時点に、支払指図全体をネットアウトする形で行われています(このような決済方式を、時点ネット決済と言います)。決済時点には、9時、13時、15時および17時過ぎ、があります。無担保コール翌日物金利の日中の動きをみると、13時決済の取引のレートが最も高く、その後、15時決済取引、17時決済取引と進むにつれて、レートが低下することが多くみられます。なお、日本銀行では、2000年末までに、即時グロス決済(支払指図をネットアウトせず、1件ごとに、グロス支払金額を、リアルタイムで決済する方式<略称RTGS>)に移行する計画です。
(4)翌日物金利の変動要因:その2――日銀当座預金残高の外生的な増減要因
金融調節以外で、民間金融機関全体の日銀当座預金残高の不足または余剰を発生させる要因は、わが国では「資金需給変動要因」と呼ばれていますが、本稿では、これを「日銀当座預金残高増減要因」と呼びます。以下では、こうした要因の内容と、その動きの予測等について説明します。
A.どのような要因があるのか
日銀当座預金残高増減要因の主なものは、(a)銀行券の発行・還収(銀行券要因)と、(b)民間金融機関と政府との間の財政資金の受け払い(財政要因)の2つです13。これらの要因の動きは、企業、家計、政府、さらには非居住者といった幅広い主体の経済活動の結果を反映するものであり、少なくとも短期的には、中央銀行にも、個々の民間金融機関にもコントロールできません。このため、海外中央銀行も含め、これらの要因は、日々の金融調節を行ううえでは、「外生的」とされています。
- (a)銀行券の発行は、例えば、企業の給与支払や行楽資金需要に伴う預金の引出しに備えるなどの目的で、金融機関が日銀当座預金から銀行券を引き出すときに生じ、日銀当座預金残高が減少するので資金不足要因となります。逆に、銀行券の還収は、例えば連休明けなどに、顧客から金融機関預金に銀行券が戻り、金融機関がそれを日銀当座預金に預け入れるときに生じ、日銀当座預金残高が増加するので資金余剰要因となります14。
- (b)財政資金の支払は、例えば、個人への年金支払や企業への公共事業費支払等のために、政府が民間金融機関に資金を支払うときに生じます。政府と民間金融機関の間の資金の受払いは、日銀当座預金口座を用いて行われるため、政府による支払いは、日銀当座預金の増加をもたらし、資金余剰要因となります。逆に、財政資金の受入とは、個人や企業から税金などを徴収するため、政府が民間金融機関から資金を引き揚げるときに生じ、日銀当座預金の減少をもたらすので資金不足要因となります。
なお、為替介入に伴う円資金決済も、日本銀行に開設された政府当座預金と民間金融機関の日銀当座預金との間で行われますので、財政要因の支払(円売り介入)または受入(円買い介入)になります。
- 13 このような中央銀行当座預金残高の変動をもたらす要因を、銀行券や財政要因等で捉える考え方は、海外主要国でも基本的には同様です。例えば、米国では、準備預金(reserves)の需要や供給を左右する要因を、factors affecting reserve balances、民間金融機関全体の「資金過不足」をもたらす外生的要因を、autonomous factorsと呼び、銀行券要因、財政要因等に分解しています。
- 14 「銀行券の発行時には、金融機関の保有銀行券が増えるのに、何故資金不足要因になるのか」という質問をよく受けます。これは、ここで言う「資金」が、民間金融機関の日銀当座預金残高を指すためです。個人や企業の場合でも、自分の預金口座から銀行券を引き出せば預金残高が減少し、その分、口座振替や自動引き落としなどの決済に使える資金が不足しますが、これと同じことです。
B.銀行券要因、財政要因の予測
このような銀行券や財政資金の変動は毎日発生しますので、民間金融機関全体の日銀当座預金の残高には、日々資金過不足が生じることとなります。従って、金融調節により市場に供給すべき資金の量を適切に決定するうえでは、銀行券要因と財政要因の変動を的確に予測することが不可欠です。これらの要因の予測に当たっては、まず、3か月程度先までの中期的な予測を行い、これを月次予測、週次予測、翌日の予想という形で、より正確になるよう見直していきます。当日も、日中数回に亘り、見直しを行っています。予測の正確を期すため、日本銀行の本支店が、民間金融機関や官庁から必要なデータを日々集めているほか、中期的な予測においては、過去の資金過不足データのパターン分析や経済・マネー指標の分析結果も加味しています。
- (a)銀行券要因については、中期的な予測は、主として過去の季節性等のパターンと、最近の伸び率のトレンドなどに基づいて行います。短期的な予測は、日本銀行本支店が、各金融機関から銀行券の受け払いの見込み額を聴取し、それを合計することによって行います。
- (b)財政要因の中期的な予測は、日本銀行が政府の諸官庁から資金の受け払いの予定データを集め、これを積み上げるとともに、企業決算等の経済指標分析も用いて行います。短期の予測は、官庁および民間金融機関からの財政資金受払見込み額の聴取に基づいて行います。
なお、日本銀行は、金融調節に関する情報開示を充実させるため、上記のようにして作成した銀行券要因、財政等要因15およびそれらの合計としての資金過不足に関する予測と実績を、月次ベースと日次ベースで公表しています16。具体的には、これらの計数は、「資金需給と調節」(通称「資金需給表」)として一表に取りまとめられ、実績については、資金過不足とともに、金融調節による資金供給(吸収)額と準備預金・日銀当座預金の計数も併せて開示しています17。日々の銀行券要因や財政要因に関し、実績のみならず予測計数まで公表しているのは、主要国の中央銀行では日本銀行のみです。日銀当座預金残高全体の増減要因は、個々の民間金融機関にとって外生的要因であるため、日次ベースでの予測公表は、資金の需給状況に関する市場参加者の見方を収斂させることを通じ、翌日物金利の安定に寄与している可能性があります18。また、こうした情報開示により、日本銀行の銀行券・財政等要因の予測精度や金融調節による資金供給量について、市場参加者が日々チェックできる訳であり、透明性の高い仕組みと言えます。
- 15 日銀当座預金残高の外生的な増減要因には、銀行券要因、財政要因のいずれにも属さない「その他要因」があります。例えば、海外中央銀行や国際機関が日本銀行に開設している円預金勘定と、民間金融機関の日銀当座預金との間の資金移動などがあります。「財政等要因」とは、財政要因とその他要因とを合計したものです。
- 16 これらの計数は、日本銀行のホームページに毎日(月次計数は毎月)掲載されます。
- 17 なお、2000年3月16日から、資金需給表の公表方式が変更されます。詳細は、5章(2)参照。
- 18 金利水準の相違や決済制度の相違(日本は時点ネット決済、米国は即時グロス決済)等から、必ずしも単純比較はできませんが、1998年中の無担保コール翌日物金利(米国はFFレートの翌日物)の前日差のボラティリティー(金利水準の標準偏差)は、日本が約0.1%、米国が約0.35%と、日本の方がかなり小さくなっています。
C.銀行券要因、財政要因の振れの大きさ
日本では、欧米に比べ、銀行券要因、財政要因ともに日々の変動幅が極めて大きいのが特徴です(この背景はBOX1参照)。例えば、1998年中の週間変動幅を日米で比較しますと、変動幅(絶対額)の平均値は、銀行券要因で日本(10,674億円)は米国(1,416億円)の約7倍、財政等要因では日本(23,547億円)は米国(5,181億円)の約4倍となっています19。この結果、日々の資金過不足全体のフレも極めて大きくなっており、その日その日の金融調節だけでは調整できない日がほとんどです。このため、予め先行きの資金過不足を予測して、早いうちから金融調節を行っておくことが必要(本章(5)A参照)であり、この意味でも、先行きの資金過不足の予測が非常に重要です。
- 19 便宜上1ドル=100円で換算。
<BOX1> わが国の銀行券・財政要因の振れは何故大きいのか?
日本において、銀行券要因、財政要因の変動が大きい理由としては、以下のような点が指摘できます。
- (a)まず、銀行券要因については、日本では経済規模に比べた銀行券の発行残高(=市中流通額)が極めて大きいのが特徴です。例えば米国と比較すると、日本の経済規模は米国の約2分の1ですが、銀行券発行残高はほぼ同額です(1998年末銀行券発行残高:日本55.9兆円、米国51.8兆円)。これは、日本では、個人の資金決済に小切手がほとんど使用されていないほか、クレジット・カードの普及率も米国に比べれば低いことなどが影響しています。銀行券が活発に使用される分だけ、曜日や季節性による変動幅も大きくなります。例えば、年間でみれば、12月には年末・年始のための、3月には新年度向けの、ゴールデン・ウィーク前にはレジャー向けの現金需要が増大するため、銀行券発行額が増大します。逆に、これらの時期の後は、市中で使われた銀行券が民間金融機関に還流してきますので、銀行券還収額が増大します。また、月末や週末に向けて銀行券発行額が増加し、月初や週初には還収額が増加するというパターンもみられます。
- (b)次に、財政要因の変動幅は、銀行券以上の大きさです。これは、a)政府預金の受け払いがすべて日本銀行に集中される仕組みとなっている20こと、b)財政資金の支払(年金等)を行う日と、財政資金の受入(税金等)を行う日が、所轄官庁ごとに別々に特定日に設定されていること、c)法人税の受入は決算期毎に年2回、年金の支払いは年6回、というように、事務処理の効率上、財政資金受払の頻度を小さく抑えていること、などが原因と考えられます。
- 20 米国では、財政資金の決済の一部が、民間銀行に開設された政府の預け金勘定(Treasury Tax and Loan Account)を通じて行われているため、決済日の異なる財政資金の受入と支払が、民間銀行において相殺され得る仕組みとなっています。ただし、民間銀行が、政府から受け入れた資金を上記の勘定に保有できる残高は、一定要件を満たす担保保有額の範囲内に限られます。
