日本銀行金融機構局
「地域金融サポートユニット」が始動
~地域金融機関の経営基盤強化に向けた取り組みを幅広く後押しする(2024年9月25日掲載)
地域経済の活性化が重要課題となっている中、2023年10月、地域金融に関する情報発信を一段と強化するため「地域金融サポートユニット」が金融機構局に創設されました。調査・分析やモニタリングなどに関わる職員が部署の枠を超えて横断的に協働し、地域金融に関する情報をより強力に発信するための仕組みです。創設以降、7カ月(2024年5月時点)の間にセミナー・ワークショップを14回、論文・レポートの公表を7本行うなど、活動は精力的です。その取り組みの実態や、職員の思いをご紹介します。
地域の課題を共に考える

地域金融サポートユニットはテーマによって協働のメンバーが変わる
「地域金融サポートユニット」(以下、ユニット)は、その名の通り、地域金融をサポートするためのユニットです。メンバー固定の組織ではなく、金融機構局の関連部署の中で、テーマによって協働のメンバーが変わります。例えば、テーマがサイバーセキュリティならシステムリスク管理の担当者を中心に、地域の不動産リスクなら地域金融機関のモニタリング担当者を中心にして、関係者が企画を具体化していきます。
もともと金融機構局には、主催セミナーなどを通して金融機関に情報提供をする「金融高度化センター」があるのですが、地域経済を支える地域金融機関の経営基盤強化に向けた取り組みをより一層後押ししようと、地域金融に関して一元的に情報提供できるユニットを発足させることになりました。取り上げるテーマは、(1)経営・リスク管理、(2)地域経済や取引先企業が抱える課題解決、(3)経営環境の変化への対応など、広範です。
その創設の意義について、金融高度化センターの在籍が長く、大学で地域活性化の講師も務める企画役の北村佳之さんはこう説明します。
「地域経済は人口減少と高齢化などの影響を強く受けています。同時に、高度成長期に整備された公共インフラが老朽化して再整備の時期を迎えており、自治体の財政も苦しくなっています。こうした状況においても、新事業への融資や企業のマッチング、自治体や企業へのアドバイスなど、長い目で見て地域経済を支え、地域金融機関自身の経営基盤を強化するためにできることは決して少なくありません。では、より具体的にどんなことができるのか、どんなやり方が考えられるのか、という情報を幅広く提供するのがわれわれの役割です。こうした情報提供のニーズは金融機関からも聞かれているところです。ユニットができたことで、情報提供のルートが一つにまとまり、地域金融機関とのパイプが太くなったのは非常に良いことだと思います」
実際に北村さんは、今年3月に「公民連携事業(PPP/PFI)の推進に向けた地域金融機関の取り組み」と題したオンラインのワークショップを企画し、自ら講演も行いました。このときには、政府が公民連携を積極的に推進しているという最新情報を伝えると同時に、各地で公民連携に取り組む当事者に登壇してもらい、四つの事例を紹介しました。こうしたセミナーをきっかけに自治体や地域金融機関の取組意欲が高まることも多いそうで、北村さんは「『今後は一段ギアを上げて頑張っていきたい』などの声を参加者から聞くと、企画者として達成感を感じます」とやりがいを口にします。
ペーパーからセミナーへ

リサーチ・ペーパーの公表後オンラインセミナーを実施
ユニットができたことで、より充実した情報発信ができた実例を紹介しましょう。リサーチ・ペーパーの公表後、さらにセミナーを実施したというケースです。
考査企画課システム・業務継続グループのグループ長で企画役の中井大輔さんは、155の取引先金融機関を対象にしたアンケート調査をもとに取りまとめたリサーチ・ペーパー「金融機関におけるクラウドサービスの利用状況と利用上の課題について」を1月に公表しました。調査先の9割以上が既にクラウドを利用しているものの、最重要領域である勘定系システムでの利用は限定的という実情を明らかにしたペーパーです。その内容の重要性から、このときは記者会見も行いました。
従来であれば、重要な情報でも発信はここまででしたが、さらに中井さんは4月にオンラインでのセミナーを実施しています。そのときを、中井さんはこう振り返ります。
「ユニットによるプラットフォームを利用することで、情報発信がしやすくなりました。地域金融機関は専門人材の確保が容易ではないもとで、対面のセミナーなどで新たに学ぼうとすれば移動の問題が生じますが、オンラインならそのハードルを下げつつダイレクトに情報をお伝えできます。言うなれば、情報格差を埋められるのです。このときは、セミナー後にペーパーへのアクセスが急増したと聞いています」
セミナーではチャットで受けた質問に回答するなど双方向性も実現し、より濃密な情報提供ができました。クラウドなどのシステム関係は日進月歩であるため、中井さんは「定期的に開催することで、最新情報をお伝えできるとともに、業界の動向をより鮮明にしていけると思います」と、今後にも期待を寄せています。
企画をどう立てるか
現状では1カ月に2回程度というハイペースで行われているセミナーですが、どのように企画されているのでしょうか。
「誰もが普段から問題意識を持って仕事をしているので、それを上司に伝える中で、また、ユニット創設以降は関係部署間でも意見交換しながら、『では、今度はそれをやろう』というようにテーマが決まっていきます。そのテーマについてどのように調査を進め、セミナーの形に仕立てていくか、担当者の役割は大きく、腕の見せどころです。登壇者の人選なども提案でき、やりがいがあります」
そう話すのは、金融高度化センター主査の中村伊知雄さんです。
中村さん自身は、昨年末に「地域金融機関による事業承継支援の取り組み」と題したワークショップを企画し、参加者に対してプレゼンテーションもしました。調査から丁寧に準備したといいます。
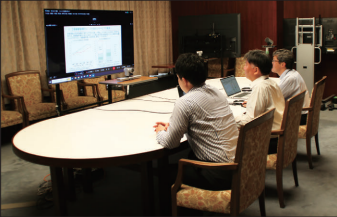
ワークショップの模様
「私自身が直接、事業承継支援実務に携わっているわけではないので、専門誌や関係する行政機関の公表資料などを読んで実務上の論点などを整理するところから始めました。同時に、日頃、地域金融機関と接しているモニタリング部署に相談し、ヒアリングさせてもらったり、登壇してもらうなら、どの金融機関がいいかなどのアドバイスも受けました。このように各部署が持っている知見を集め、リソースの幅を広げてより有機的にシナジーを利かせられるのがユニットの意義だと感じています」
と中村さん。当日は、中小企業の事業承継が親族承継から第三者承継にシフトしつつある状況を踏まえた支援の取り組みなどを伝えました。
開催後はアンケート調査も行い、より有意義な企画や運営ができるように努めています。「もっと事例紹介を」「銀行と信用金庫を分けてほしい」などの声があるそうで、「模索しながらやっています」と中村さんは話します。
念入りな準備と運営

端末の稼働確認など入念な準備が不可欠
ところで、こうした情報提供の陰には、運営の苦労もあります。現状のセミナー・ワークショップはオンラインのみの実施ですが、安定的な通信状態の下で完遂するには、入念な準備が不可欠です。その中心を担っているのは、金融高度化センター企画役補佐の小澤康裕さんです。ここに至るまでには試行錯誤があったと語ります。
「安定的な通信を確保するため、ユニット創設前から金融高度化センターでは、担当者みんなで知恵を出し合いながらノウハウを培ってきました」
例えばその一つは、セミナー開催時のモニター確認とバックアップです。講演中は参加者と同じ画面を表示し、映像や音声の乱れがないかをリアルタイムにチェックしています。同時に、講演者のそばにサブ端末を起動させておき、万一、講演中の端末に不具合が生じても、すぐにサブ端末に切り替えができる態勢を取っています。
また、ワークショップでは全国の地域金融機関の方々が登壇することもありますが、これらの方々とも、必ず事前に本番と同じ環境で、疎通確認や、資料投影の確認をしています。
「幸いにして一度も講演途中で中止に至ったことはありませんが、今でも『これで終わります』のアナウンスを聞くまで気が抜けません。こうしたノウハウを蓄積していくことは一朝一夕にできることではないので、これを活用していけるのがユニットの一つのメリットだと感じます」
協働でできること
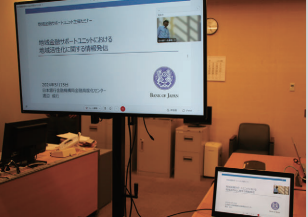
2024年5月には地域活性化に関するセミナーを開催
準備という点では、テーマ選定や企画立案のための動き出しも必要です。ここで重要な役割を担うのが、オフサイト・モニタリングなどで地域金融機関と日々接している金融第二課です。ユニットにおける役割を、同課の企画役の天野賢治さんはこう説明します。
「全国の金融機関のさまざまな層と接点があるので、共通する課題や関心がリアルに見えてきます。今なら、DXや人手不足問題、高齢化などです。そうした話から得た感触を、金融高度化センターと意見交換しています。また、金融第二課が専門とするリスク管理などについては、セミナーの企画を提案することもあります。このように異なる視点や情報を融合することで、よりニーズに合った情報を提供していけると感じています」
地域金融機関との交流が深い金融第二課だけに、セミナー終了後には「もっと詳しく知りたい」などの意見を受けることも多くなったといいます。そうした体験から、天野さんはユニットの意義をこう話します。
「地域金融機関には、さまざまな情報をいただいているので、そこから見えた共通の課題や役立つ情報を還元できるのは意味のあることです。枠組みを作ることがゴールではないので、セミナーでの反応や疑問を受け取りながら、さらに期待に応えられる情報を提供していければと思います」
(肩書などは2024年6月上旬時点の情報をもとに記載)
